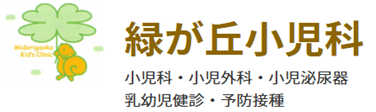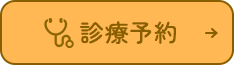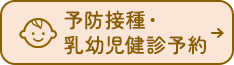小児泌尿器科について
 小児泌尿器科とは、主にお子様の泌尿器に関わる病気やトラブルに対して診療を行う診療科です。泌尿器とは、腎臓や尿管、尿道、膀胱に加え、男性の場合は精巣や陰茎、女性の場合は子宮、膣など、尿の生成から排出までの一連の器官を指します。
小児泌尿器科とは、主にお子様の泌尿器に関わる病気やトラブルに対して診療を行う診療科です。泌尿器とは、腎臓や尿管、尿道、膀胱に加え、男性の場合は精巣や陰茎、女性の場合は子宮、膣など、尿の生成から排出までの一連の器官を指します。
泌尿器の病気やトラブルは、こども大人問わず様々な年代の方に見られますが、お子様の場合、成長の途中にあるため、大人とは異なる泌尿器の病気を引き起こすことがあります。こどもの泌尿器の治療が行える医療機関は限られており、専門の病院へ受診するには、紹介状が必要なこともあるため、受診のハードルが高く感じられるかもしれません。
当院では、お子様の泌尿器の問題に関する診察と超音波による診断が可能です。お子様の包茎や陰唇癒合については当院でも治療が可能です。なお、外科手術が必要な場合には近隣および当院と連携する高度小児専門医療機関をご紹介いたします。
お子様に気になる症状が現れている場合や、なんか変?と違和感がある場合なども、お気軽にご相談ください。
小児泌尿器科で
よくご相談いただく症状
男の子に多いご相談

- トイレが近い・日中にお漏らしをすることがある
- おしっこのにおいや色、出る回数が気になる
- おちんちんが痛い・かゆい
- おちんちんの先の部分が赤くなったり、腫れたりしている
- おちんちんの先から膿が出る、または膿のようなものがある
- 包茎のため皮がむけず、きれいに洗えない
- 精巣(睾丸)が触れない・片方しか触れない(片方しかない)
- 精巣の大きさや左右差が気になる
- おちんちんの大きさや形、色、においが気になる
など
女の子に多いご相談

- トイレが近い・日中にお漏らしをしてしまうことがある
- おねしょがなかなか治らない
- 小学生になっても夜におねしょが続いている
- おしっこのにおいや色、出る回数が気になる
- 排尿のときに痛がる
- おしっこに血が混じっていることがある
- おしっこが出にくそうにしている
- デリケートゾーンのかゆみや痛みを訴える
など
小児泌尿器科で
よくご相談いただく病気
夜尿症(おねしょ)
 夜尿症とは、5歳以降のおねしょのことを言います。夜尿症は原因によって、夜間の尿の量が多いタイプや膀胱の尿の蓄積量が少ないタイプ、睡眠・覚醒に障害があるタイプなど様々な種類に分類されます。夜尿症は多くは10歳頃までに自然に改善しますが、中には何か別の疾患が原因で引き起こされていることもあります。また、夜尿症が治らないと、お泊りに行けないなどの強いコンプレックスを生むようになります。夜尿症は生活習慣の見直しで改善することがありますので、就学後までお子様の夜尿症が長引いている場合は当院までご相談ください。
夜尿症とは、5歳以降のおねしょのことを言います。夜尿症は原因によって、夜間の尿の量が多いタイプや膀胱の尿の蓄積量が少ないタイプ、睡眠・覚醒に障害があるタイプなど様々な種類に分類されます。夜尿症は多くは10歳頃までに自然に改善しますが、中には何か別の疾患が原因で引き起こされていることもあります。また、夜尿症が治らないと、お泊りに行けないなどの強いコンプレックスを生むようになります。夜尿症は生活習慣の見直しで改善することがありますので、就学後までお子様の夜尿症が長引いている場合は当院までご相談ください。
包茎
包茎とは、慢性的にペニスの先端が包皮で覆われて亀頭が出ない状態です。乳幼児期のお子様はほとんどが包茎の状態で、成長とともに徐々に亀頭が現れるようになります。ただし、乳幼児期でも包皮によって先端の尿の出口が塞がれてしまうと細菌が繁殖して、痛みやかゆみが生じたり、赤くなったり、膿が出たりすることがあります。また、放置すると腎臓や膀胱で炎症を起こしてしまう可能性があります。このような状態になってしまうと治療が必要になりますが、お子様の包茎は軟膏による治療で8割程度はが改善します。無理やり包皮を剥くと、場合により包皮に傷がついて包皮が硬くなり包茎が悪化すことがあります。お子様のペニスのことで気になる症状が続いている場合は一度ご相談ください。
亀頭包皮炎
亀頭包皮炎とは、亀頭や包皮に汚れが溜まり、細菌が感染して炎症を起こした状態です。主な症状は、亀頭が腫れて痛みが出る、排尿時に痛みを感じる、黄色い膿が出るなどがあります。乳幼児期のお子様はもともと包茎であり、汚れた手で触れたり、きちんと洗えてなかったりなどして、亀頭包皮炎を引き起こしやすくなります。再発もしやすいため、お子様に気になる症状が続いている場合にはぜひ一度ご相談ください。繰り返すと包皮の先端が硬くなり、包茎が悪化し排尿に支障が出て最悪の場合は手術が必要になることがあります。多くの場合、成長とともに免疫力も上がり包皮もむけて、亀頭包皮炎にはならないようになってきます。
停留精巣
停留精巣とは、陰嚢内に精巣(睾丸)が入っていない状態で、多くの場合は先天的な異常が原因の病気です。出生直後に精巣が陰嚢内に降りてなくても、生後6か月までに陰嚢内に精巣が自然に降りてくることもあります。しかし、6か月以上経っても改善しない場合には手術などの専門的な治療が必要になります。停留精巣の問題は、精巣が温まることによる①妊孕制の低下(男性不妊)②精巣の悪性化(癌化)と精巣が固定されてないことによる③精巣捻転の危険性、などです。手術を行うかどうかは「厚生労働省が定める停留精巣ガイドライン」に沿って決定します。また、精巣の位置が安定していない遊走精巣(移動性精巣)も存在します。精巣の位置の評価や手術の必要性に関しては、専門的な知識や経験も重要です。当院では手術は行えませんが、停留精巣および遊走精巣の診断と手術の必要性の判断は可能です。手術が必要と判断された場合には、地域または連携する専門の医療機関をご紹介いたします。手術後の経過観察も可能です。
鼠経ヘルニア
足の付け根(鼠径部)に、お腹とつながった袋状の構造が残ってしまい、そこに腸などお腹の中の臓器が出入り(脱腸)して、ふくらみが出たり戻ったりする病気です。女の子の場合は卵巣が出ることもあります。泣いたり、いきんだりするとこのふくらみが目立つことがあります。出たり戻ったりする状態では問題ありませんが、臓器が戻らなくなってしまう「ヘルニア陥頓(かんとん)」という危険な状態になることもあります。陥頓の状態を放置すると入り込んだ腸管などの臓器の壊死(腐ること)や男の子の場合は、精巣への血流が途絶えて、徐々に萎縮する危険性があります。当院では、診察と超音波検査で診断を行います。また陥頓に対する対応も可能です。さらに、必要に応じて手術ができる小児専門の医療機関を紹介いたします。
陰嚢水腫
陰嚢水腫とは、足の付け根(鼠径部)から陰嚢にかけての袋状の部分に液体がたまった状態です。多くの場合、生後間もなく見られ、9割は2歳頃までに自然に治癒します。ただし、お腹の中とつながっていて水が出入りする「交通性陰嚢水腫(こうつうせい・いんのうすいしゅ)」の場合は、自然に治らないこともあります。当院では超音波検査で診断を行い、手術が必要な場合は、近隣または連携する小児専門の医療機関をご紹介いたします。
尿路感染症(膀胱炎、他)
尿路感染症とは、尿道口から大腸菌などの病原菌が入り、尿が通る経路(尿道・膀胱・腎臓など)に炎症を起こす病気です。その中でも、膀胱炎は、膀胱粘膜に大腸菌などの病原菌が入りこみ炎症を引き起こす病気です。一般的に男の子より尿道が短い女の子に多く見られます。膀胱炎は初期の段階では炎症によって膀胱・尿道が影響を受けて頻尿を引き起こし、症状が進行すると排尿時に痛みを伴うようになります。さらに、この状態を放置すると、腎臓にまで菌がおよび腎盂腎炎を引き起こすこともあります。特に小児では、生まれつき膀胱から腎臓に尿が逆流する膀胱尿管逆流症(VUR)があり、放置すると腎盂腎炎を繰り返して腎臓に障害を起こすこともあるため注意が必要です。VURは自然に軽快することも多い疾患ですが、外科的治療が必要な場合があり、治療が可能な小児の専門施設への紹介が必要です。VURの診断には、造影検査が必要であり、疑われた場合も小児の専門施設での検査が必要です。また、膀胱炎などの尿路感染は院内でできる尿検査によって診断が可能です。お子様の頻尿や排尿痛など気になる症状が現れている場合には一度当院までご相談ください。
陰唇癒合
陰唇癒合とは、左右の陰唇がくっついて膣の入り口が見えにくくなっている状態です。主におむつをつけている時期の女の子に見られます。慢性的な外陰部の炎症や感染が原因と考えられており、幼児期以降で、排尿障害(排尿時の痛み・飛び散るや時間がかかるなど)を訴えて発見されることがあります。経験上、年齢が上がるにつれてこの融合は強固になり、全身麻酔による手術が必要になることもあります。当院では、2歳以下のお子様の場合は、麻酔を使わずに癒合部分を剥がす処置が可能です。健診で偶然に発見した場合はその場で陰唇癒合の切開治療を行います。当院では、2歳以下の健診の時にチェックし、必要あればその場で簡単な治療を行います。成長に伴い羞恥心も芽生えてくるため、早期発見が重要です。気になる場合はお早めにご相談ください。