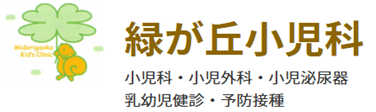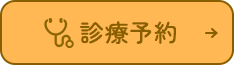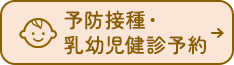「発熱・咳・嘔吐・下痢があるお子様」および「ご家族など周りに感染症(新型コロナ・インフルエンザ・RS ウイルス感染・ノロウイルスなど)の方がいる場合」は、必ず予約時に問診票へ記載をお願いします。
こどもの繰り返す発熱について
 こどもは大人に比べて免疫機能が未発達のため、頻繁に発熱を起こします。発熱を繰り返すことで徐々に免疫機能を獲得し、大人になると滅多に発熱を起こさなくなります。
こどもは大人に比べて免疫機能が未発達のため、頻繁に発熱を起こします。発熱を繰り返すことで徐々に免疫機能を獲得し、大人になると滅多に発熱を起こさなくなります。
こどもの発熱は多くの場合、特に心配は要りませんが、以下のような症状が現れている場合には早急に医療機関を受診するようにしましょう。
すぐに受診した方が良い場合
- 生後3か月未満で38℃以上の発熱がある
- 発熱でぐったりしている
- 発熱とともに呼吸困難やけいれんを起こしている
- おしっこの回数や量が減少している
- ミルクや食事をほとんど摂取できない
こどもの繰り返す発熱の原因
生まれたばかりの頃はまだ十分な免疫が備わっていません。免疫機能は成長とともに少しずつ発達していくため、大人なら感染しないような病原体でも、こどもにとっては対応しきれず、感染してしまうことがあります。また、こどもは体に対して皮膚の表面積が広く、体重あたりの熱の影響を受けやすい特徴があります。さらに、汗を出す汗腺が未熟なため、大人のようにしっかり汗をかくことができません。その代わり、皮膚から直接熱を逃がして体温を調節しています。このため、長時間暑い場所にいたり、厚着させすぎたり、運動や遊びで興奮したりするだけでも、体温が上がりやすくなります。
こどもの繰り返す発熱で
考えられる病気
感染症
RSウイルス感染症
 RSウイルス感染症とは、風邪の原因ウイルスの一つであるRSウイルスに感染することで発症する感染症で、2歳までのこどものほぼ全員が感染します。
RSウイルス感染症とは、風邪の原因ウイルスの一つであるRSウイルスに感染することで発症する感染症で、2歳までのこどものほぼ全員が感染します。
ほとんどの場合、感染しても軽症ですが、乳幼児の場合は免疫機能が未熟なため、発熱や鼻水、咳、呼吸困難、食欲減退などの症状を引き起こすことがあります。また、重症化すると入院治療が必要になるケースもあります。特に、生後6か月未満の赤ちゃんや早産で生まれて赤ちゃん、心臓に基礎疾患がある赤ちゃんはリスクが非常に高いので、早めの対応と集中治療が可能な小児の高度医療機関への紹介が必要になります。
インフルエンザ
インフルエンザとは、風邪の原因ウイルスの一つであるインフルエンザウイルスに感染することで発症する感染症で、主な症状は38℃以上の発熱や鼻水、咳、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感などが挙げられます。インフルエンザは事前にワクチン接種することで発症や重症化リスクを抑えることが可能です。重篤な合併症に肺炎や脳症があり、特にインフルエンザ脳症は、重篤な後遺症の合併や命に係わる危険性があります。インフルエンザワクチンは、生後6か月以降から接種可能です。発症から2日以内だと、内服・吸入・点滴のインフルエンザの治療薬が有効でウィルスの増殖を抑え、症状の改善や合併症の予防に役立ちます。
溶連菌感染症
溶連菌感染症とは、溶血性連鎖球菌という細菌に感染することで引き起こされる感染症です。主な症状は38℃以上の発熱の他、のどの痛みやリンパ節の腫れ、発疹などが挙げられます。溶連菌感染症の治療は抗生物質を10日ほど続けて服用します。リウマチ熱・急性糸球体腎炎など様々な合併症があり、症状改善後も抗生物質は最後まで服用する必要があります。
ヘルパンギーナ
ヘルバンギーナとは、エンテロウイルスやコクサッキーウイルスに感染することで発症する感染症です。夏に流行する夏風邪の一種で、主な症状は発熱やのどの赤み、水疱などが挙げられます。5歳以下が全体の90%以上を占めます。一般的に発熱は2~3日ほどで改善するケースがほとんどで経過も良好です。
突発性発疹
突発性発疹とは、ヒトヘルペスウイルスに感染することで引き起こされる感染症で、一般的に乳幼児に多く、ほとんどが生後6か月頃から2歳までに発症します。高熱が突然出現し、発症すると39℃以上の発熱が3日以上続き、その後熱が下がってきたころに全身に発疹が現れます。発疹は数日で自然に消失します。中には熱性けいれんを併発するケースもあります。
咽頭結膜熱(プール熱)
咽頭結膜熱とは、一般的にプール熱と呼ばれている感染症で、アデノウイルスに感染することで発症します。発熱、咽頭炎、結膜炎の3症状が主な特徴で、4~7日ほどの高熱やのどの赤みに加え、頭痛や結膜炎を併発するケースがあります。プールを介して感染することがあるため、俗に「プール熱」とも呼ばれています。また、アデノウイルスは数十種類あるため、流行り目や胃腸炎、重度の肺炎、出血性膀胱炎など様々な疾患を引き起こします。通常、1週間程度で自然に治癒します。
おたふく風邪
(流行性耳下腺炎)
流行性耳下腺炎とは、一般的におたふく風邪と呼ばれている感染症で、唾液を分泌する耳下腺にムンプスウイルスが感染することで発症します。主な症状は発熱や耳下腺の痛みで、耳下線が腫れることで顔がおたふくのように膨らむ特徴があります。また、これら症状に加えて頭痛や嘔吐を併発している場合には髄膜炎を合併している恐れがあるため、注意が必要ですその他の合併症として難聴や精巣炎や卵巣炎があります。おたふく風邪は、感染力が強く幼稚園・保育園・学校などで広がりやすい傾向があります。日本では任意接種ですが、事前にワクチン接種することで予防が可能です。
水痘(みずぼうそう)
水痘とは一般的にみずぼうそうと呼ばれている感染症で、水痘・帯状疱疹ウイルスに感染することで発症します。感染者の咳・くしゃみの飛沫や発疹を触ることで感染します。主な症状はかゆみを伴った水疱や発熱などで、水痘は主に頭皮に現れます。水痘は事前にワクチン接種することで予防が可能です。水痘は治療薬(抗ウィルス薬)があり、発症して72時間以内に服用することが重要です。すべての発疹が痂皮化(かさぶた)するまで、登校・登園は控える必要があります。
麻疹(はしか)
麻疹とは麻疹ウイルスに感染することで発症する感染症です。感染力が非常に強く空気感染もするため、免疫をもっていない場合は感染するとほぼ100%発症します。主な症状は発熱や鼻水、咳、目やになどで、これら症状が2~3日継続します。発熱はいったん治まりますが、その後再び発熱(39℃以上の高熱)し、同時に全身に赤い発疹が発生する特徴があります。発疹は顔面から始まり、体幹、四肢へ広がり、4~5日ほど経過すると自然に消失していきます。肺炎、中耳炎、脳炎などの合併症があります。麻疹は事前にワクチン接種することで予防が可能です。お子様が1歳になったら必ずワクチン接種するようにしましょう。
その他
上記のような感染症以外にも、熱中症や川崎病、自己免疫疾患、甲状腺疾患、悪性腫瘍など様々な病気によって熱が出ることがあります。そのため、熱が下がらない場合や発熱を何度も繰り返している場合には、これらの疾患が隠れている可能性があり、対症療法では治らずに病状が進行します。できるだけ早めに当院までご相談ください。
こどもの繰り返す発熱の対処法
体温測定について
 一般的には、37.5℃以上を発熱、38.0℃以上を高熱と言いますが、熱の高さで重症だと判断するのではなく、熱以外に具合の悪いところはないか注意してみましょう。また、平熱の把握や測定のタイミングや環境も重要です。
一般的には、37.5℃以上を発熱、38.0℃以上を高熱と言いますが、熱の高さで重症だと判断するのではなく、熱以外に具合の悪いところはないか注意してみましょう。また、平熱の把握や測定のタイミングや環境も重要です。
平熱の把握
平熱には個人差があり、一日の中でも体温は変動します。一般的に朝は低く、夕方にかけて少し高くなります。同じ条件で、食前や食事と食事の間の時間に測定しましょう。
体温測定のタイミング
食後(授乳後)や入浴後、運動後、眠いときなどは体温が高くなりやすい特徴があります。30分ほど時間をおいてから体温を測るようにしましょう。
脇の下が汗で湿っていないか
脇に汗が残ったままだと、正確な体温測定ができないことがあります。汗を拭きとって乾いた状態で体温を測りましょう。
水分摂取について
こどもは大人に比べて体の水分の割合が多いのですが、新陳代謝が活発で水分が失われやすいことや、汗をかく機能や腎臓の機能が未熟なことから、脱水症状を起こしやすい特徴があります。そのため、熱が出ている時はこまめに水分補給することが大切です。経口補水液や、白湯、麦茶などを飲ませてあげてください。ただし、下痢や嘔吐を起こしている場合は、糖分や電解質も不足します。低血糖を起こさないようにするため、経口補水液など糖分を含む飲み物やみそ汁の上澄みなどを選んでください。
母乳やミルクの場合
乳幼児の発熱の場合は、普段通り母乳やミルクを飲ませてください。ミルクは通常の濃さで、薄める必要はありません。母乳やミルクをあまり飲まない場合は、経口補水液などを飲ませてあげましょう。ただし、果汁などは下痢を悪化させることもあり、与える場合は赤ちゃん用のものがお勧めです。
食事摂取について
発熱時は、食事が十分にできないことも多くあります。その場合は、無理して食べさせずに、水分補給を優先してください。乳幼児は肝機能が未熟なためエネルギーを蓄積できず低血糖を起こしやすいため、糖分を含む経口補水液やスープを摂るようにしてください。お子さんは、吐いて喉が渇くと一気に水分を摂取し、再び嘔吐することがあります。このような場合は、体から失われるもののほうが多くなります。また、食べ物や水分の種類によっては下痢を悪化させることがあります。胃腸炎で嘔吐や下痢が続いている場合は、お薬以外に水分や食事に注意することが重要です。
水分摂取について
熱の出始めは、悪寒で体が震えることがあります。その時は毛布で体を包んで温めるようにします。震えが止まって血色が改善したら、今度は逆に熱がこもりすぎないように掛け物を薄くしたりなど調整します。汗が出てくると、徐々に体温も下がっていきますが、汗で体が冷えないように、着替えたり、汗をこまめに拭き取ることが重要です。(熱くてしんどそうな場合は、冷却ジェルシートを貼ったり、保冷剤をガーゼなどで包んでから首や脇の下、太ももの付け根を冷やしたりすると効果的です。ただし、無理に体を冷やす必要はありません。)
解熱剤の使用について
発熱に伴って、のどの痛みやだるさによって、水分摂取が十分にできない、眠れない場合は、解熱剤を使用することも大切です。当院では、小さなお子様でも比較的副作用が少ないアセトアミノフェンを主成分とするカロナールなどを処方しています。小さなお子さんは、痛みやだるさを訴えられません。アセトアミノフェンは、解熱だけでなく痛みをとる効果もありますので、熱の程度に関わらず使用することも大切です。