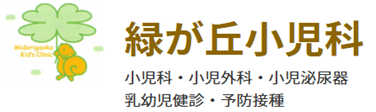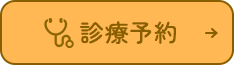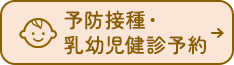夜尿症(おねしょ)について
 夜尿症とは、一般的におねしょと呼ばれているもので、5~6歳になってもおねしょをしていると夜尿症と診断されます。乳幼児期は排尿器官が発達していないため、頻繁におねしょをしますが、5~6歳頃になると排尿器官が発達するため、おねしょは自然になくなります。しかし、中には何らかの原因によって、おねしょが続くケースもあります。小学生にもなると羞恥心も芽生えているため、自信損失や学校のお泊まりイベントへの不安など、悩みを抱えているこどもも少なくありません。当院では、夜尿症でお悩みのお子様やご家族を対象に診断や治療をしています。根性や気合でどうにかしようとせずに、まずは一度ご相談ください。
夜尿症とは、一般的におねしょと呼ばれているもので、5~6歳になってもおねしょをしていると夜尿症と診断されます。乳幼児期は排尿器官が発達していないため、頻繁におねしょをしますが、5~6歳頃になると排尿器官が発達するため、おねしょは自然になくなります。しかし、中には何らかの原因によって、おねしょが続くケースもあります。小学生にもなると羞恥心も芽生えているため、自信損失や学校のお泊まりイベントへの不安など、悩みを抱えているこどもも少なくありません。当院では、夜尿症でお悩みのお子様やご家族を対象に診断や治療をしています。根性や気合でどうにかしようとせずに、まずは一度ご相談ください。
夜尿症(おねしょ)の原因
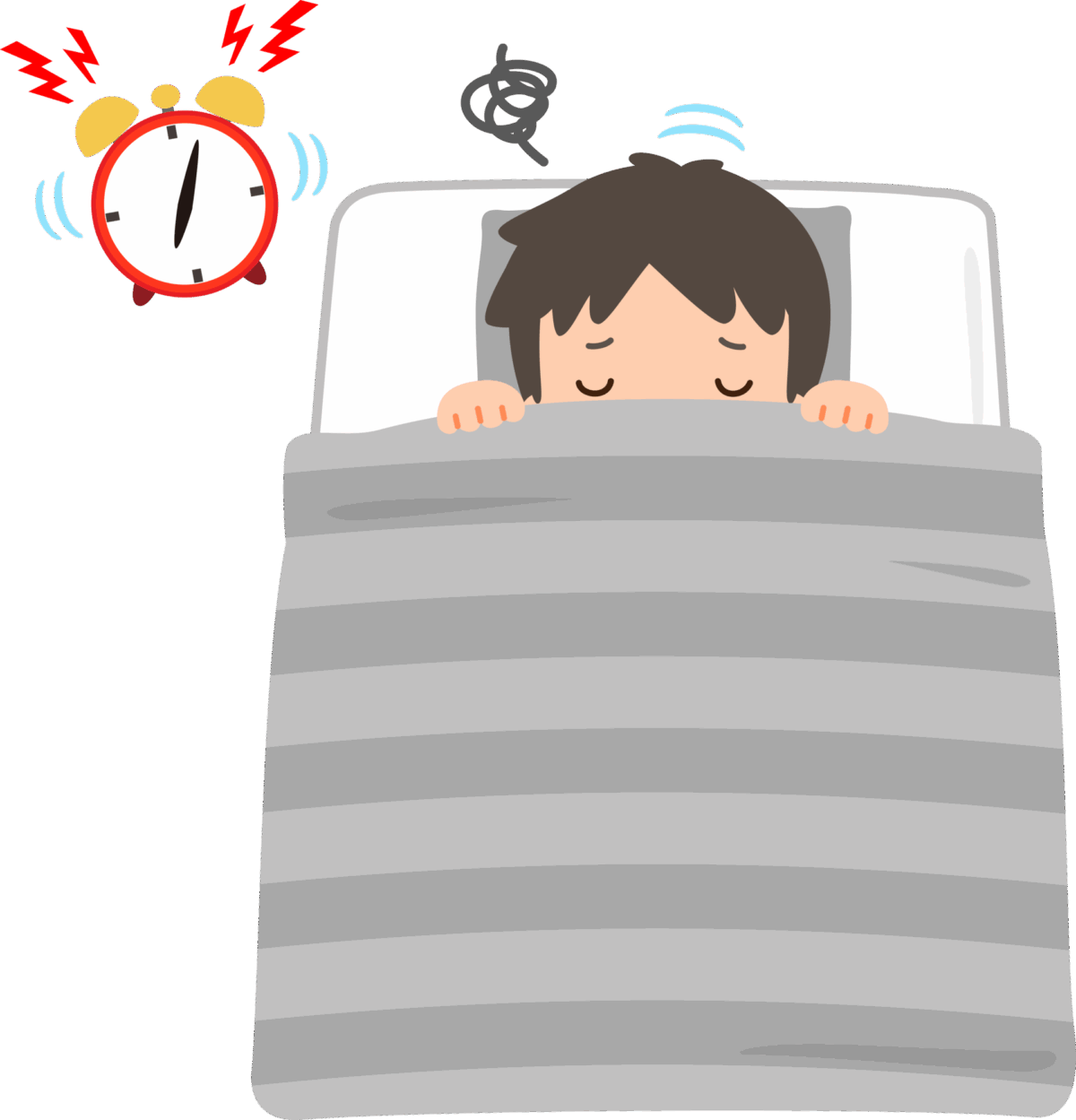 夜尿症の主な原因は、夜中に目が覚めにくい(覚醒障害)という背景を基に、以下の3つのタイプに分類されます。
夜尿症の主な原因は、夜中に目が覚めにくい(覚醒障害)という背景を基に、以下の3つのタイプに分類されます。
- 多尿型(夜間の尿の量が多くなる):夜間に多く分泌されて尿量を減らす働きのある「抗利尿ホルモン」が十分に分泌されないことが原因です
- 膀胱型(膀胱の容量が少ない):膀胱に尿をためておく力がまだ発達していないため、夜間の尿を十分に蓄えられないことが原因です
- 混合型:多尿型と膀胱型の両方の特徴がみられます
夜尿症(おねしょ)の症状
夜尿症の主な症状は、夜間寝ているときに本人が意図せず、尿を漏らしてしまうことです。医学的には「5歳以上になっても、おねしょが週2~3回のペースで3か月以上続くもの」とされています。
夜尿症(おねしょ)の
診断・検査
夜尿症の原因には、泌尿器科的疾患や内分泌疾患、脊髄疾患などの可能性もあります。一般的に夜尿症のお子様の5%弱にこれらの疾患が見つかるため、まずは診察や検査によって、これらの疾患の有無を確認します。疾患が無かった場合は、夜間の尿量の測定や膀胱容量の測定をします。
夜尿症(おねしょ)の治療
生活習慣の見直し
夕方からの水分摂取を控える
水分は午前中によく摂るようにして、午後から寝る前まで(特に寝る3時間前)は水分を控えるようにしましょう。夕食は水分とともに塩分も控えめにすると効果的です。また、夕食後におやつを食べると、のどが乾いて水分を摂りたくなってしまうため、3時のおやつがおすすめです。
排尿抑制訓練
夜尿症の原因の一つに、膀胱の尿をためる容量が少ないことが挙げられます。そのため、排尿抑制訓練を実施します。おしっこを途中で止めたり、昼間のおしっこをできるだけ我慢させたりなどの訓練をして、少しずつ我慢できる時間を長くし、1回の膀胱容量や1日の排尿量を記録していきます。
無理やり起こしてトイレに行かせない
夜間に無理やり起こしておしっこをさせてしまうと、抗利尿ホルモンの分泌が低下して症状が悪化する可能性があります。
身体を冷やさない
身体が冷えると夜尿症を助長します。お子様の手足が冷たいなど冷え性が疑われる場合には、湯船につかったり、炭酸系の入浴剤を使用したりなど対策しましょう。
シール作戦
シールを準備し、上手にできたら自分でシールを貼らせて、きちんと褒めてあげましょう。このように自分でできたことを可視化することで、本人の自信向上やモチベーション向上にも繋がります。
薬物療法・アラーム療法
以上のような取り組みをしても1か月の夜尿回数が半分以下まで減少しない場合は、薬物療法やアラーム療法を検討します。薬物療法は夜尿症を引き起こしている原因によって使い分けます。多尿型の場合には寝る前に抗利尿ホルモンを補充し、膀胱型の場合にはアラーム療法を実施したり、膀胱容量を増加させるために抗コリン薬を使用したりします。混合型の場合には、これらの治療を同時に行います。アラーム療法とは、お子様が就寝中お漏らしをした際に自動的にアラームが作動して覚醒を促すものです。3か月間で約60%のこどもに有効であると報告されています。当院ではアラーム療法は行っていないため、必要に応じて専門の医療機関をご紹介いたします。