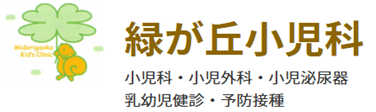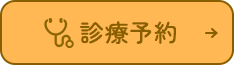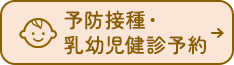小児皮膚科について
 小児皮膚科とは、新生児〜中学生のお子様を対象に皮膚に関する専門的な診療を行う診療科です。お子様の皮膚は大人に比べて薄い上に、皮膚の水分量や皮脂が少なく、外敵から皮膚を守るバリア機能も弱いことから、かぶれや湿疹、感染症といったトラブルを引き起こしやすい傾向があります。そのため、少しでも異変が生じた際にはできるだけ早めのケアを行うことが大切になります。特に乳児期早期の皮膚トラブルは、アトピー性皮膚炎への移行や食物アレルギーの発症、その後、気管支ぜんそくやアレルギー性鼻炎への移行(アレルギーマーチ)が問題になります。
小児皮膚科とは、新生児〜中学生のお子様を対象に皮膚に関する専門的な診療を行う診療科です。お子様の皮膚は大人に比べて薄い上に、皮膚の水分量や皮脂が少なく、外敵から皮膚を守るバリア機能も弱いことから、かぶれや湿疹、感染症といったトラブルを引き起こしやすい傾向があります。そのため、少しでも異変が生じた際にはできるだけ早めのケアを行うことが大切になります。特に乳児期早期の皮膚トラブルは、アトピー性皮膚炎への移行や食物アレルギーの発症、その後、気管支ぜんそくやアレルギー性鼻炎への移行(アレルギーマーチ)が問題になります。
当院の小児皮膚科では、経験豊富な医師がお子様の年齢や症状に応じて、皮膚トラブルの治療の他、再発を防ぐための入浴および保湿など適切なケアを指導しています。お子様のスキンケアに不安があるまたは、お子様に気になる症状が現れている場合には、ぜひお気軽に当院までご相談ください。
小児皮膚科で
よくご相談いただく症状
- 肌のかさつき(ガサガサしている)
- 肌の赤みが続く
- 発疹(ぶつぶつ)がある
- 肌のかゆみが続く
- 皮がむける
- 肌がジュクジュクしている
- 虫刺され後の腫れが治らない
- 夜間にかゆみが強くなる
など
小児皮膚科で
よくご相談いただく病気
乳児湿疹
乳児湿疹とは、「脂漏性皮膚炎」や「新生児ざ瘡」、「おむつかぶれ」などの乳児期(特に生後2・3週~数か月まで)の皮膚トラブルの総称になります。生後1〜2か月ほどの乳児期はまだ皮膚を守るバリア機能が弱いため、ちょっとした刺激でも様々な皮膚トラブルを起こしやすい傾向があり、注意が必要です。
脂漏性皮膚炎
乳児の脂漏性皮膚炎とは、生理的な脂腺機能の亢進により、生後2週頃より発症する皮膚に黄色いかさぶた状のものができる乳幼児期の皮膚疾患の一つです。主に肌が擦れる部分や皮脂腺が集中する頭皮・額・耳周囲などに発症しますが、痒みを伴うことはありません。一般的に生後3か月頃までの乳児に多く見られますが、その後自然に消失していきます。対処法としては、コットンにベビーオイルやオリーブオイルを浸してかさぶたのようなものをふやかし、その後、きれいに洗浄するようにしましょう。
新生児ざ瘡
新生児ざ瘡とは、生後2週間頃から赤や白のニキビのような発疹がみられることをいいます。お母さんのホルモンの影響で赤ちゃんの皮脂分泌が活発になることが主な原因で鼻や頬の周囲にしばしば見られます。対処法としては、1日に1回は低刺激の石鹸を泡立てて優しく洗い、温めのお湯でしっかりすすぐことによって肌を清潔に保ち、入浴後は、肌が湿っているうちに、しっかり保湿するなど毎日のスキンケアが重要です。
おむつかぶれ(接触性皮膚炎)
おむつかぶれとは、おむつに触れている部分の皮膚が、尿や便などの刺激によって肌荒れを起こし、赤いぶつぶつなどができる状態で刺激性接触性皮膚炎です。臀部や陰嚢、陰茎、大陰唇などに後発し、症状が重くなると皮膚がただれてしまうこともあります。主な対処法としては、こまめにおむつを取り替えて、交換時にすぐにはおむつを着用せず、外して乾かし、湿潤環境を予防することで、乾いたタオルやコットンで押し拭きするか、弱酸性のおしりふきなどで肌を清潔に保ちます。また、亜鉛華軟膏や白色ワセリンをたっぷり塗り排泄物の暴露から皮膚を保護します。ただれている部分には、ステロイド外用薬などを塗って症状を抑えることが有効です。ステロイド外用薬を使用しても、改善しない場合は、カンジダ症を引き起こしている可能性がありますので、その際は抗真菌外用薬による治療を行います。
汗疹(あせも)
 汗疹(あせも)とは、汗を多くかいた後に生じる発疹です。症状は人によって様々で、白っぽい水ぶくれになる場合や、かゆみ・痛みを伴う赤い丘疹になる場合があります。一般的にお子様は汗をかきやすく、皮膚もデリケートで、汗腺の多い肘・膝の内側部分や首に多く見られますが、蒸れやすいおむつ内・後頭部・背中にもできやすくなります。大人でも発熱や、スポーツや仕事などで長時間高温の環境に晒されると発症することがあります。
汗疹(あせも)とは、汗を多くかいた後に生じる発疹です。症状は人によって様々で、白っぽい水ぶくれになる場合や、かゆみ・痛みを伴う赤い丘疹になる場合があります。一般的にお子様は汗をかきやすく、皮膚もデリケートで、汗腺の多い肘・膝の内側部分や首に多く見られますが、蒸れやすいおむつ内・後頭部・背中にもできやすくなります。大人でも発熱や、スポーツや仕事などで長時間高温の環境に晒されると発症することがあります。
汗疹はまずは予防が重要です。適切な住環境(服装)・入浴でのケア・スキンケアなどを指導します。汗疹ができてしまった場合の主な治療は、ステロイド外用薬などの使用を中心としたスキンケアを行います。ステロイド外用剤は、お子さんの年齢と汗疹の部位や程度に応じた適切な強さと量の選択が重要です。汗疹は肌のバリア機能が低下していると生じやすいため、汗をかいた後はシャワーを浴びたり、難しい場合はこまめに着替えたり、保湿して肌の潤いを保つことが大切です。
皮脂欠乏症、皮脂欠乏性湿疹
皮脂欠乏症とは、一般的に乾燥肌と呼ばれており、主に皮膚の皮脂が不足することで引き起こされます。皮脂は、細菌やウイルスの侵入を防いだり、肌の潤いを保ったりする役割があり、皮脂の量が少ないと、肌が乾燥してかゆみやかさつき、ひび割れなどのトラブルを引き起こしやすくなります。こどもの皮膚は皮脂分泌量や角質水分量が少なく、バリア機能も未熟なため、皮膚の乾燥をきたしやすい状態にあります。生後4か月頃までは、お母さんのホルモンの影響で皮脂の分泌が多く保たれていますが、4か月を過ぎるとその分泌が急激に減少します。そのため、乳幼児は皮膚が乾燥しやすく、皮脂欠乏による肌トラブルが起こりやすくなります。また、お子様はかゆみを我慢できずに皮膚表面を掻きむしってしまいがちです。皮膚を掻きむしってしまうと炎症を起こして皮脂欠乏性湿疹を引き起こし、皮膚のバリア機能が損なわれる恐れがあります。皮脂欠乏性湿疹の段階ですぐに医療機関を受診して治療を行えば問題ありませんが、悪化して慢性化するとアトピー性皮膚炎へと進行する可能性もあるため、注意が必要です。乾燥肌が気になる場合やかゆみが続いている場合は、当院までご相談ください。
じんましん
 じんましんとは、アレルゲンの刺激によって、かゆみのある湿疹が生じるアレルギー性疾患です。通常では数10分~数時間で自然に消失することがほとんどで、軽症の場合は抗アレルギー薬を使用することで症状は治まります。ただし、重症の場合はステロイドや免疫抑制の内服薬を使用することもあります。原因となるアレルゲンには様々な物質がありますが、特定のアレルゲンが同定されることは少なく、対症療法が基本となります。食べ物や薬によるじんましんの場合にはアナフィラキシーショックを起こす可能性もあるため、注意が必要です。アナフィラキシーショックになると、アレルゲンに接触してから短時間で全身に湿疹が広がり、呼吸困難や嘔吐、腹痛などが生じます。アナフィラキシーショックの場合、放置すると命にかかわることもあるため、発疹以外の異変を感じたら、迷わず救急車を呼んでください。
じんましんとは、アレルゲンの刺激によって、かゆみのある湿疹が生じるアレルギー性疾患です。通常では数10分~数時間で自然に消失することがほとんどで、軽症の場合は抗アレルギー薬を使用することで症状は治まります。ただし、重症の場合はステロイドや免疫抑制の内服薬を使用することもあります。原因となるアレルゲンには様々な物質がありますが、特定のアレルゲンが同定されることは少なく、対症療法が基本となります。食べ物や薬によるじんましんの場合にはアナフィラキシーショックを起こす可能性もあるため、注意が必要です。アナフィラキシーショックになると、アレルゲンに接触してから短時間で全身に湿疹が広がり、呼吸困難や嘔吐、腹痛などが生じます。アナフィラキシーショックの場合、放置すると命にかかわることもあるため、発疹以外の異変を感じたら、迷わず救急車を呼んでください。
アトピー性皮膚炎
アトピー性皮膚炎とは、かゆみのある湿疹が慢性的に生じるアレルギー性疾患です。こどもから大人まで幅広く見られますが、生後2か月を過ぎたころの乳児から発症することもあります。乳児の場合は、顔(特に頬や耳の周り・口の周り・顎)などに多く、しばしば体幹、四肢に下降し、かゆみを伴います。乳児湿疹との鑑別が難しいケースもあるため、気になる症状がある場合は当院までご相談ください。
幼小児期のアトピー性皮膚炎は、頸部、四肢関節部の病変が多く、顔や首、背中、肘、脇、お腹、膝などに赤色のジュクジュクした湿疹が左右対称に発生する特徴があります。その後、成長に伴って皮膚の乾燥部分が広がっていき、思春期以降には、上半身(頭・頸・胸・背)に皮疹が多い傾向になります。アトピー性皮膚炎は自然治癒することはないため、医療機関を受診して適切な治療を行う必要があります。保湿を含めたスキンケアと適切なステロイドなどの外用の使用と痒みのコントロールが重要です。治療せずに放置すると、大人になっても症状が持続する可能性もあるため、一度医療機関に受診されることをおすすめします。
手足口病
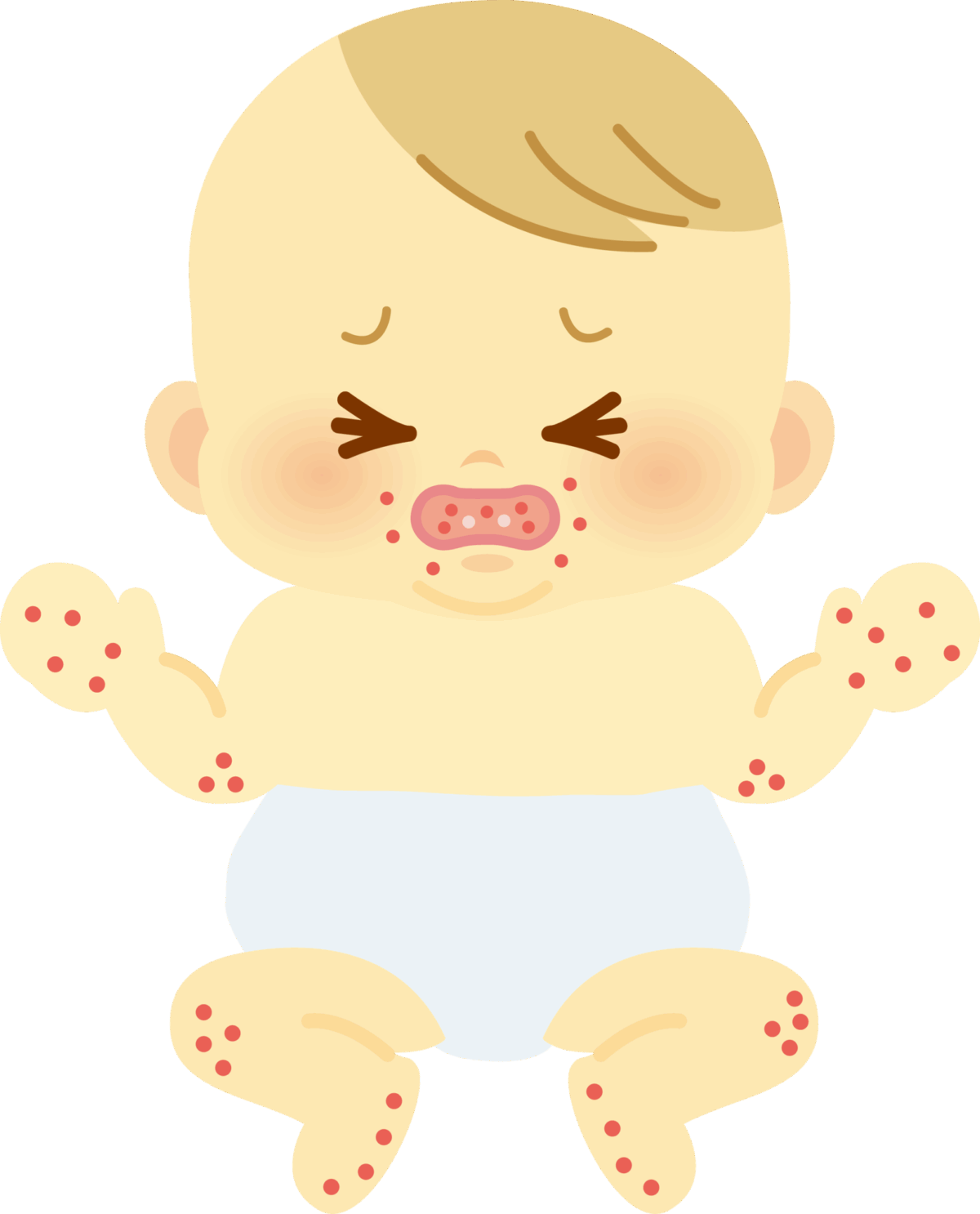 手足口病とは、その名の通り、手足や口の中に水ぶくれや赤みが生じる感染症です。コクサッキーウイルスやエンテロウイルスなどのウイルスが原因となります。感染している方の咳やくしゃみを吸い込んだり、水ぶくれの中身や便に含まれるウイルスが手やおもちゃなどを介して口に入ることで感染します。感染してから3~5日後の潜伏期間を経て、発症します。主な症状は、感染した部位に2~3mm程度の水疱性の発疹が現れることに加え、3人に1人の割合で軽い発熱を伴うこともあります。痛みやかゆみがあることもあり、口の中が痛くて食べられないことがあります。一般的に症状は数日で自然に治まるケースがほとんどです。症状がないまたは軽くて日常生活に支障がない(場合は園や学校を休む必要はありません。まれに高熱が出ることや、口の中が痛くて食べれず脱水になることもあります。手足口病を治療するための有効な薬はないため、経過をみながら症状に応じた治療を行います。熱がなく元気で普段の食事がとれる場合は、登園・登校できます。大人にも感染し、子供よりも症状が重くなる場合があります。子供が使ったタオルや食器を触ることで感染します。
手足口病とは、その名の通り、手足や口の中に水ぶくれや赤みが生じる感染症です。コクサッキーウイルスやエンテロウイルスなどのウイルスが原因となります。感染している方の咳やくしゃみを吸い込んだり、水ぶくれの中身や便に含まれるウイルスが手やおもちゃなどを介して口に入ることで感染します。感染してから3~5日後の潜伏期間を経て、発症します。主な症状は、感染した部位に2~3mm程度の水疱性の発疹が現れることに加え、3人に1人の割合で軽い発熱を伴うこともあります。痛みやかゆみがあることもあり、口の中が痛くて食べられないことがあります。一般的に症状は数日で自然に治まるケースがほとんどです。症状がないまたは軽くて日常生活に支障がない(場合は園や学校を休む必要はありません。まれに高熱が出ることや、口の中が痛くて食べれず脱水になることもあります。手足口病を治療するための有効な薬はないため、経過をみながら症状に応じた治療を行います。熱がなく元気で普段の食事がとれる場合は、登園・登校できます。大人にも感染し、子供よりも症状が重くなる場合があります。子供が使ったタオルや食器を触ることで感染します。
水いぼ(伝染性軟属腫)
水いぼとは、皮膚に伝染性軟属腫ウイルスが感染することで発症する感染症です。最初は局所的に発生しますが、水いぼが潰れることでウイルスが他の部分に広がって感染箇所が拡大することがあります。一般的には、水いぼは、発症から数か月〜数年で自然に消失しますが、湿疹やアトピー性皮膚炎がある場合は、感染リスクが高まりますので注意が必要です。感染している方の皮膚に直接触れるだけでなく、家族間で衣服やタオルを共有することでも感染します。なお、学校保健安全法の規定では水いぼの感染者のプールは禁止していませんが、園や学校によっては自主規制していることもあります。
とびひ(伝染性膿痂疹)
とびひ(伝染性膿痂疹)とは、あせもや虫刺され、すり傷、湿疹などができた部分を掻きむしってしまうことで、黄色ブドウ球菌やレンサ球菌などの細菌が入りこみ、感染を起こす病気です。主な症状は、皮膚が赤く腫れる、じゅくじゅくする、水ぶくれができるなどの特徴が挙げられます。また、とびひを起こしている皮膚を触った手で触れると、体中に感染が拡大したり、他の人にもうつったりしてしまいます。シャワーや入浴で毎日しっかり皮膚を清潔に保つことが予防において大切です。主な治療は、軽症の場合には抗菌薬を患部に塗布します。重症の場合には抗生物質の内服薬を使用することもあります。予防を行っても治らない場合は当院までお気軽にご相談ください。