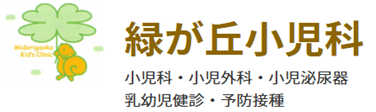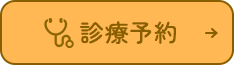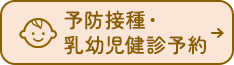「発熱・咳・嘔吐・下痢があるお子様」および「ご家族など周りに感染症(新型コロナ・インフルエンザ・RS ウイルス感染・ノロウイルスなど)の方がいる場合」は、必ず予約時に問診票へ記載をお願いします。
こどもの長引く咳について
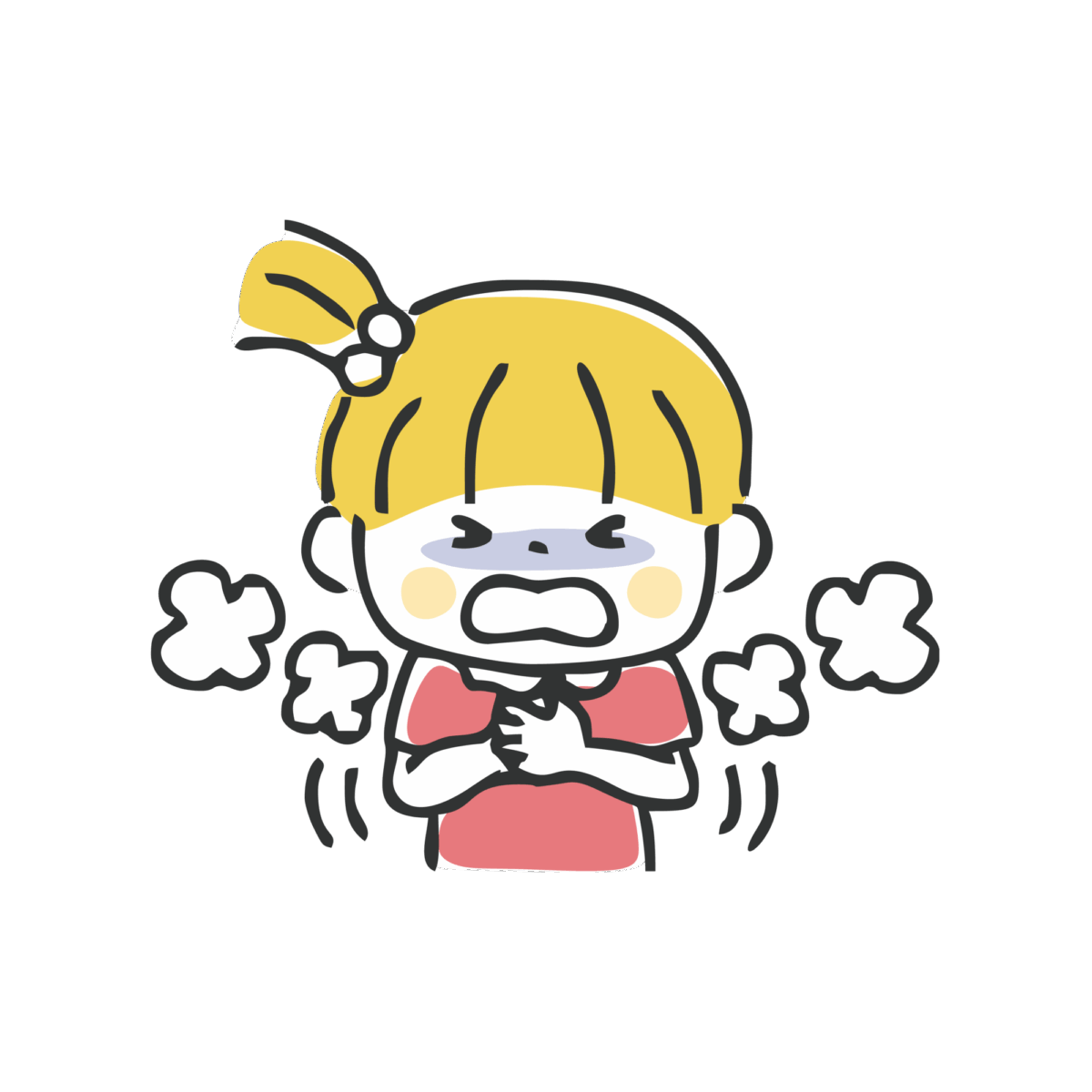 お子様の気道は大人に比べて細くて敏感なため、わずかな刺激や分泌物にも反応しやすく、咳が出やすくなっています。また、お子様は風邪をひいたあとも、しばらく咳だけが続くことがあります。これは、気道の炎症によって咳が出やすくなっていたり、回復の途中で分泌される痰に刺激されて咳が出たりするためです。咳がなかなか治らない場合は、咳以外の症状(発熱や痰の有無)や、咳が強くなる時間帯やきっかけ(運動後・夜間など)をメモしていただくと、診察時に症状を伝えやすくなり、原因の特定にも役立ちます。咳をすると全身の筋肉が使われるため、頻繁に咳が続くと体力を消耗してしまいます。目安として、2週間以上咳が続いているようであれば、一度当院までご相談ください。
お子様の気道は大人に比べて細くて敏感なため、わずかな刺激や分泌物にも反応しやすく、咳が出やすくなっています。また、お子様は風邪をひいたあとも、しばらく咳だけが続くことがあります。これは、気道の炎症によって咳が出やすくなっていたり、回復の途中で分泌される痰に刺激されて咳が出たりするためです。咳がなかなか治らない場合は、咳以外の症状(発熱や痰の有無)や、咳が強くなる時間帯やきっかけ(運動後・夜間など)をメモしていただくと、診察時に症状を伝えやすくなり、原因の特定にも役立ちます。咳をすると全身の筋肉が使われるため、頻繁に咳が続くと体力を消耗してしまいます。目安として、2週間以上咳が続いているようであれば、一度当院までご相談ください。
すぐに受診した方が良い場合
以下の項目に1つでも該当する場合には、早めに医療機関を受診するようにしましょう。
-
顔色が悪い(唇の色が紫になっている)
- 咳によって十分に睡眠がとれていない
- 近づくと呼吸音が聞こえる
- 「ヒューヒュー」「ゼーゼー」という喘鳴が続いている
- のどに異物が詰まっている可能性がある
- 呼吸とともに肩が上下に動く(肩呼吸)
- 呼吸とともに鎖骨の上や肋骨の下が凹む(陥没呼吸)
- 呼吸とともに小鼻が開閉する(鼻翼呼吸)
など
こどもの長引く咳の原因
誤飲と誤嚥
誤飲とは異物が食道に混入してしまう状態を言い、誤嚥とは気道に混入してしまう状態を言います。誤飲の場合は通常通りの呼吸や発声ができていれば特に問題はありませんが、誤嚥の場合は呼吸困難や窒息を引き起こす恐れがあるため、注意が必要です。
ただし、誤飲の場合でもボタン電池や2個以上の磁石などを飲み込んでしまった場合には早急に治療を行う必要がありますので、救急外来を受診するか、救急車を呼んでください(ボタン電池は1時間以内に食道や消化管に損傷を引き起こします。また、複数の磁石の場合は、腸を挟んでくっつくと腸閉塞や穿孔などの重篤な状態を引き起こす可能性があります。どちらも診断にはレントゲンが必要で、全身麻酔下の摘出処置になります。誤飲後は早い対応が重要ですので、処置が可能な高度医療機関を最初から受診することをお勧めします。
気道異物
気道異物とは、空気の通り道である気道に異物が混入して呼吸困難を引き起こす状態を言います。異物によって気道が完全に塞がれてしまうと窒息を起こす危険があるため、早急に治療を行う必要があります。一方、気道に多少の隙間がある場合には、ヒューヒュー・ゼーゼーという喘鳴を起こしたり、咳が続いたりします。この状態では完全に呼吸が妨げられてはいませんが、異物が気道の狭い部分に移動すると窒息を起こす危険があるため、いずれにしても早急に治療を行う必要があります。異物の場所を特定するために、レントゲン検査や胸部CT検査、内視鏡検査を実施することもあります。これらの検査が必要と判断した場合、連携する高度医療機関をご紹介いたします。呼吸が急激に悪化する場合は、救急車を呼んで、応急処置を行いながら処置が可能な高度医療機関を受診する必要があります。
心因性咳嗽(がいそう)
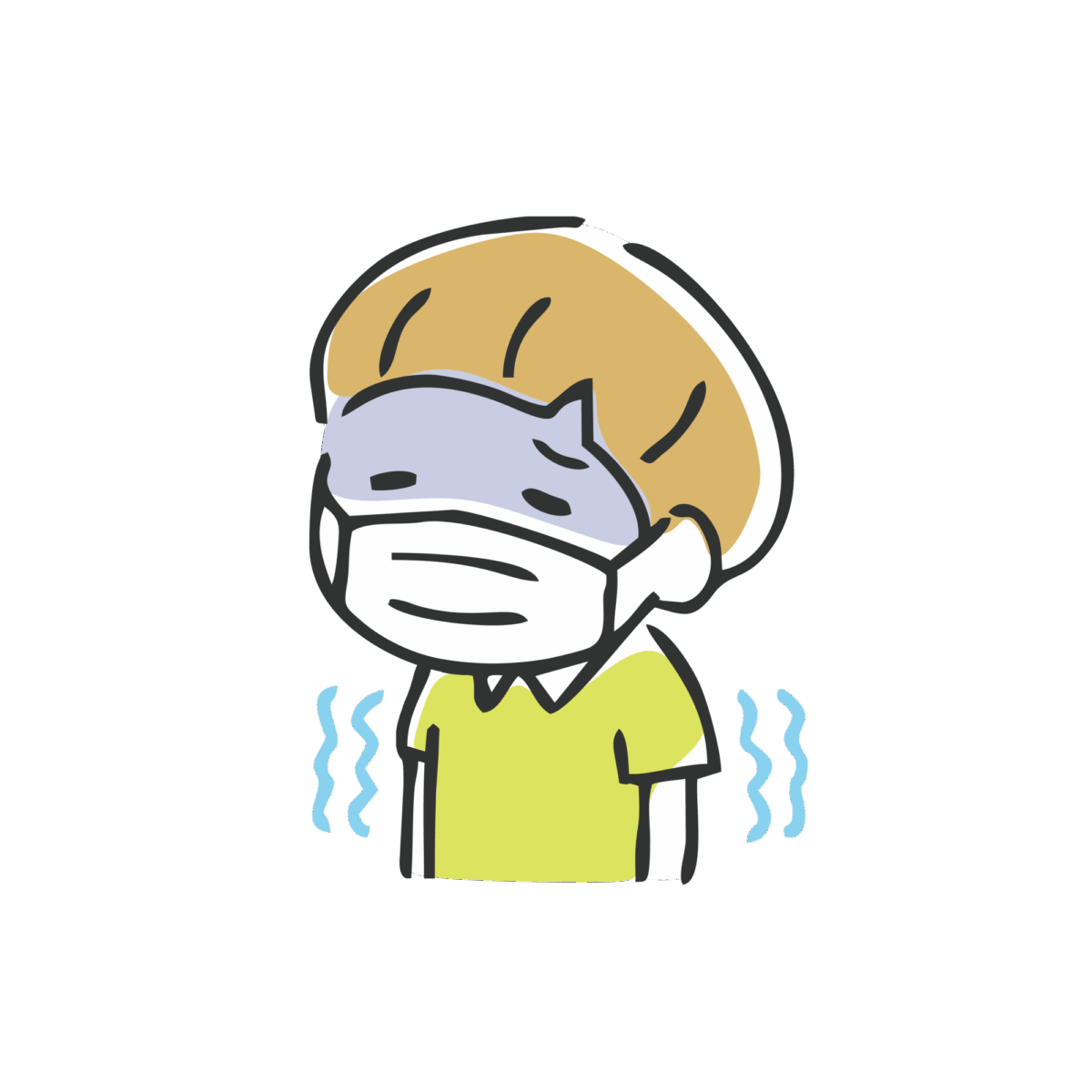 心因性咳嗽とは、過度な緊張やストレスなどによって、咳を引き起こす疾患です。咳は日中が多く、寝ているときはほとんど出ないのが特徴です。また、季節は関係なく1年通して発症します。心因性咳嗽を明確に診断する方法はないため、検査によって気管支喘息や咳喘息、副鼻腔炎、胃食道逆流症の可能性が排除された場合に心因性咳嗽と診断されます。
心因性咳嗽とは、過度な緊張やストレスなどによって、咳を引き起こす疾患です。咳は日中が多く、寝ているときはほとんど出ないのが特徴です。また、季節は関係なく1年通して発症します。心因性咳嗽を明確に診断する方法はないため、検査によって気管支喘息や咳喘息、副鼻腔炎、胃食道逆流症の可能性が排除された場合に心因性咳嗽と診断されます。
こどもの長引く咳で考えられる病気
風邪(感冒・風邪症候群)
風邪は主にウイルス感染によって鼻やのどの粘膜に炎症が起きることで発症します。原因となるウイルスにはRSウイルスやコロナウイルス、アデノウイルス、ライノウイルス、コクサッキーウイルス、ヒトメタニューモウイルスなど様々な種類があります。主な症状は、発熱や鼻水、鼻づまり、咳、全身倦怠感などが挙げられます。咳症状は10日~2週間ほど続いて自然に治まることが多いですが、炎症の程度によって気道が過敏になると、さらに長引くケースもあります。咳症状が数週間もの長い間継続している場合には、感染後咳嗽の可能性があります。必要に応じて血液検査を行い、レントゲン検査が必要な場合は連携している医療機関をご紹介いたします。
クループ症候群(急性喉頭気管支炎)
クループ症候群とは、主にウイルスが原因となり、のどが炎症を起こして腫れて、空気の通り道である気道が狭くなり、呼吸しづらい状態になる病気です。6か月から3歳までの乳幼児に多く見られます。犬やオットセイが鳴く声に似た「ケンケン」「クォーンクォーン」という咳が特徴です。その他に、声がかすれたり、息を吸い込むときにゼーゼーしたりなどの症状が現れます。軽症の場合は、自宅で加湿したり、安静に過ごしたりして自然に治ることがあります。悪化すると、鎖骨の上や肋骨の下が呼吸するたびに凹む陥没呼吸を引き起こします。主な治療は吸入やステロイド薬の投与となりますが、1歳未満の乳幼児が罹患すると酸素投与が必要になることもあります。入院加療が必要な場合がありますので、夜間などは、近くの入院加療が可能な小児科のある施設を受診するようにしてください。昼間に咳や呼吸の仕方がいつもと違ってなんだかおかしいとお気づきの場合は、当院までご相談ください。
気管支喘息
クループ症候群とは、主にウイルスが原因となり、のどが炎症を起こして腫れて、空気の通り道である気道が狭くなり、呼吸しづらい状態になる病気です。6か月から3歳までの乳幼児に多く見られます。犬やオットセイが鳴く声に似た「ケンケン」「クォーンクォーン」という咳が特徴です。その他に、声がかすれたり、息を吸い込むときにゼーゼーしたりなどの症状が現れます。軽症の場合は、自宅で加湿したり、安静に過ごしたりして自然に治ることがあります。悪化すると、鎖骨の上や肋骨の下が呼吸するたびに凹む陥没呼吸を引き起こします。主な治療は吸入やステロイド薬の投与となりますが、1歳未満の乳幼児が罹患すると酸素投与が必要になることもあります。入院加療が必要な場合がありますので、夜間などは、近くの入院加療が可能な小児科のある施設を受診するようにしてください。昼間に咳や呼吸の仕方がいつもと違ってなんだかおかしいとお気づきの場合は、当院までご相談ください。
百日咳
百日咳とは、百日咳菌に感染することで引き起こされる感染症です。一般的に感染から1週間~10日ほどの潜伏期間を経てから発症します。カタル期と呼ばれる最初の1~2週間は鼻水や咳など、一般的な風邪の症状が現れ、次第に咳がひどくなっていきます。この咳は夜間に特に強くなりやすく、咳の勢いで嘔吐することもあります。その後、コンコンという短い咳が連続して起きた後、最後に大きく息を吸い込む時にヒューと鳴る、百日咳特有の咳がみられます。この咳がみられるようになる頃は、抗菌薬が効かなくなってしまうため、流行状況などから鑑みて早期に診断し、治療することが大切です。乳幼児の場合は、この特有の咳は出ず、無呼吸発作を起こすことがありますので、注意が必要です。近年は、従来効果があった抗菌薬の耐性菌が流行っています。咳が2週間以上続く場合は、早めにご相談ください。百日咳のワクチン(三種混合・四種混合・五種混合)は、4~12年間で免疫が切れることが知られています。また、6か月未満特にワクチンを接種していない乳児は重症化のリスクが高くなります。
胃食道逆流症(GERD)
胃食道逆流症とは、胃酸や胃の内容物が何らかの原因によって逆流を起こし、食道の粘膜が炎症を起こす病気です。この逆流で気管支が刺激されると咳が生じます。生まれつき下部食道括約筋の働きに問題がある場合や、もともと問題がなくても生まれたばかりの赤ちゃんは食道や胃の機能が未発達なため、食道と胃のつなぎ目がゆるみ逆流が生じることがあります。乳幼児期によくみられますが、成長に伴い機能も発達するため、多くの場合は自然に治ります。しかし、逆流により何度も嘔吐したり、繰り返し気管支炎や肺炎を起こす場合は、検査や治療が必要です。乳児期早期に哺乳中または哺乳直後にゼコゼコしたり、咳が出たりするお子さんも胃食道逆流症が疑われます。成長とともに改善する疾患ですので、当院ではまずは哺乳の仕方の指導と内服薬の併用で経過をみます。症状が重い場合は、造影検査や入院での検査が必要です。院長は大学病院で多くのGERDのお子さんの治療経験があり、まずは、内服薬と哺乳の指導で対応しますが、症状が重い場合は検査が必要です。外来での対応には限りがあるため、その際は連携している専門の医療機関へ紹介いたします。
こどもの長引く咳の対処法
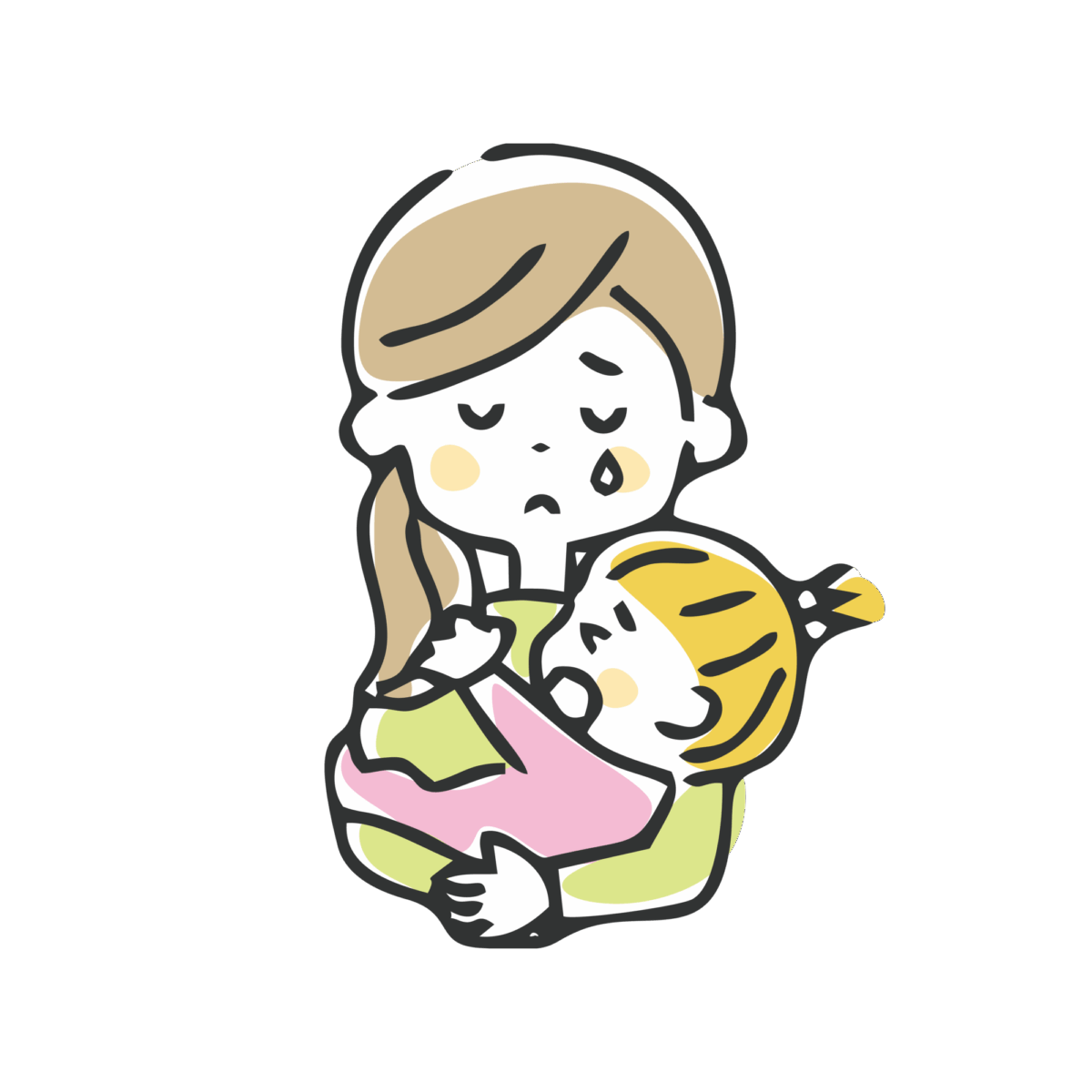 泣いていると、咳がひどくなるので、まずは落ち着かせて泣き止ませます。それから、以下の方法を試してみてください。
泣いていると、咳がひどくなるので、まずは落ち着かせて泣き止ませます。それから、以下の方法を試してみてください。
上体を起こす
眠れないほどの激しい咳が夜間に起きている場合には、いったん上体を起こして背中や腰にクッションなどを入れて安静状態を保ちましょう。枕だけを高くすると気道が狭くなって咳が悪化する恐れがあるため、注意しましょう。
冷たいお水を飲む
夜間、咳が続く場合には、何回かに分けて冷たい水を少しずつ飲むと症状が改善することがあります。ただし、柑橘類など糖分を含む飲み物はのどを刺激して悪化してしまう可能性があるため、避けるようにしましょう。
はちみつを飲む(1歳以上)
はちみつには抗菌作用があるため、就寝前にはちみつを飲むと、咳を改善する効果が期待できます。※ただし、1歳未満のお子様は腸内環境が整っていないため、乳児ボツリヌス症を発症して命にかかわることもあるため、絶対に控えてください。
部屋を加湿する
乾燥はのどを刺激して咳症状を助長します。そのため、冬場など空気が乾燥する季節は、加湿器を使用したり、濡れたタオルを屋内に干したりして、室内湿度を60%程度に維持するようにしましょう。ただし、加湿器は長い間洗浄しないとカビを発生させますので、お手入れした上で使用してください。また、就寝前に暖かい飲み物を飲むことでも、のどの乾燥を防ぐ効果が期待できます。