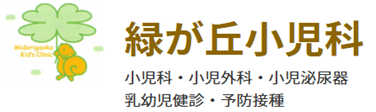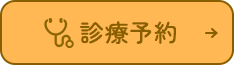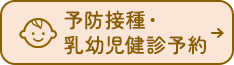こどもの肛門周囲膿瘍について
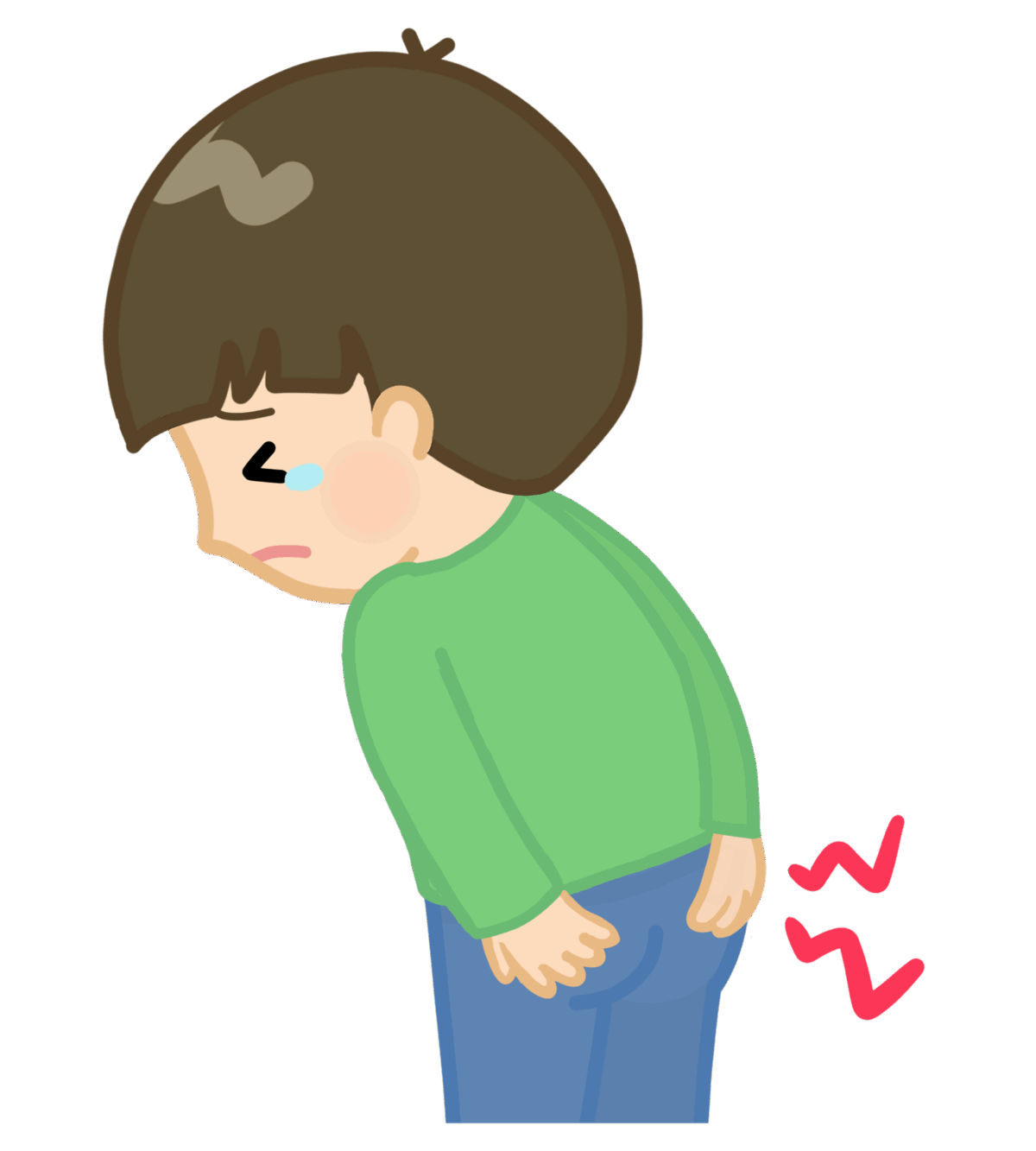 肛門周囲膿瘍とは、肛門の周りに生じる化膿性の炎症です。一般的に生後2歳まで(特に生後1か月から1歳まで)のお子様に多く見られ、女の子よりも男の子に多い傾向があります。肛門周囲の皮膚が尿や便によって炎症・化膿を起こすことによって起こります。また、炎症部分から膿が流れ出すと「痔ろう」へと進行する恐れがあるため注意が必要です。ただし、乳幼児の痔ろうは大人とは異なり、多くの場合手術治療は必要とせず、1歳頃までに治ることがほとんどです。主な治療は、整腸剤や漢方薬を使用します。
肛門周囲膿瘍とは、肛門の周りに生じる化膿性の炎症です。一般的に生後2歳まで(特に生後1か月から1歳まで)のお子様に多く見られ、女の子よりも男の子に多い傾向があります。肛門周囲の皮膚が尿や便によって炎症・化膿を起こすことによって起こります。また、炎症部分から膿が流れ出すと「痔ろう」へと進行する恐れがあるため注意が必要です。ただし、乳幼児の痔ろうは大人とは異なり、多くの場合手術治療は必要とせず、1歳頃までに治ることがほとんどです。主な治療は、整腸剤や漢方薬を使用します。
こどもの肛門周囲膿瘍の原因
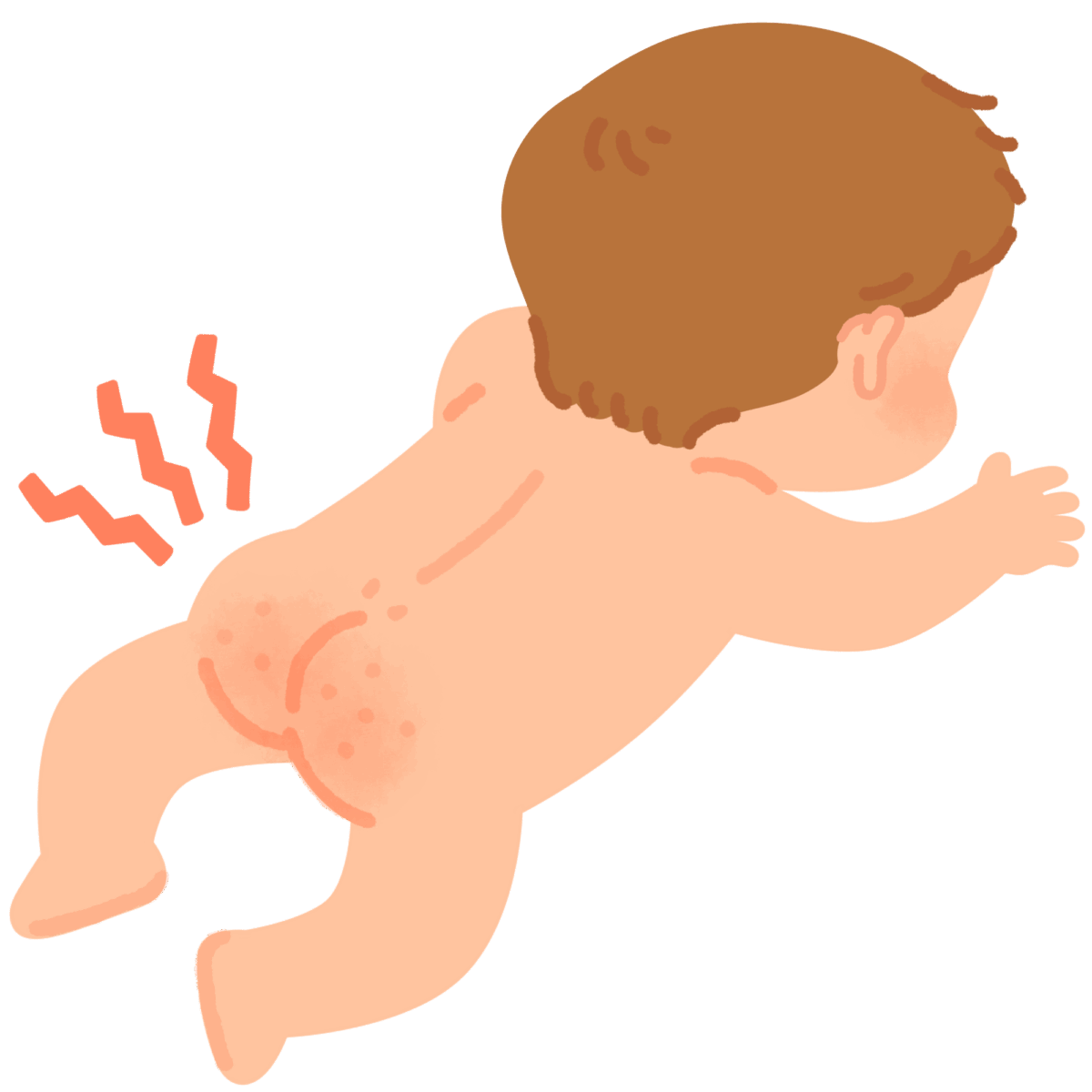 よくある原因はおむつかぶれです。おむつの中に残った尿や便が皮膚を刺激し、炎症が起こりやすくなります。特に乳児の便は、母乳やミルクの乳糖によって乳酸菌が増え、酸性が強くなります。肌は本来弱酸性ですが、強い酸性の便に長時間触れると、皮膚のバリア機能が低下し、さらに刺激を受けやすくなります。また、乳児は大人と比べて免疫機能が未発達なため、細菌感染による炎症が起こりやすいのも特徴です。
よくある原因はおむつかぶれです。おむつの中に残った尿や便が皮膚を刺激し、炎症が起こりやすくなります。特に乳児の便は、母乳やミルクの乳糖によって乳酸菌が増え、酸性が強くなります。肌は本来弱酸性ですが、強い酸性の便に長時間触れると、皮膚のバリア機能が低下し、さらに刺激を受けやすくなります。また、乳児は大人と比べて免疫機能が未発達なため、細菌感染による炎症が起こりやすいのも特徴です。
こどもの肛門周囲膿瘍の症状
乳幼児の肛門周囲膿瘍の主な症状は、肛門周囲の痛みやかゆみ、腫れ、赤みなどが挙げられます。また、炎症部が化膿して膿が流出すると、痔ろうへと進行することもあります。初期の段階では肛門周囲が赤く腫れ、小さなしこりのようなものが、肛門の両横(3時と9時)1個〜数個でき始めます。さらに、病状が進行すると、炎症部分に膿が溜まっていきます。また、周囲も赤くはれ痛がるようになり、中には発熱や食欲減退などの症状が見られるケースもあります。赤ちゃんの痔ろうの特徴は、9割以上が男の子、2歳までに自然に治る、できる位置が肛門の両横(3時・9時)にできることが特徴です。赤ちゃんのお尻が赤く腫れている、お尻に触れるとしこりがあるといった場合は、できるだけ早く当院までご相談ください。
こどもの肛門周囲膿瘍の
診断・検査
乳幼児の肛門周囲膿瘍の診断は、まず肛門周囲の状態を詳しく観察します。その後症状に応じて血液検査などを実施することもありますが、一般的には必要ありません。出ている膿を検査して細菌の種類を特定することもありますが、抗菌剤の投与は必ずしも重要でないので特に検査は必要ありません。。
こどもの肛門周囲膿瘍の治療
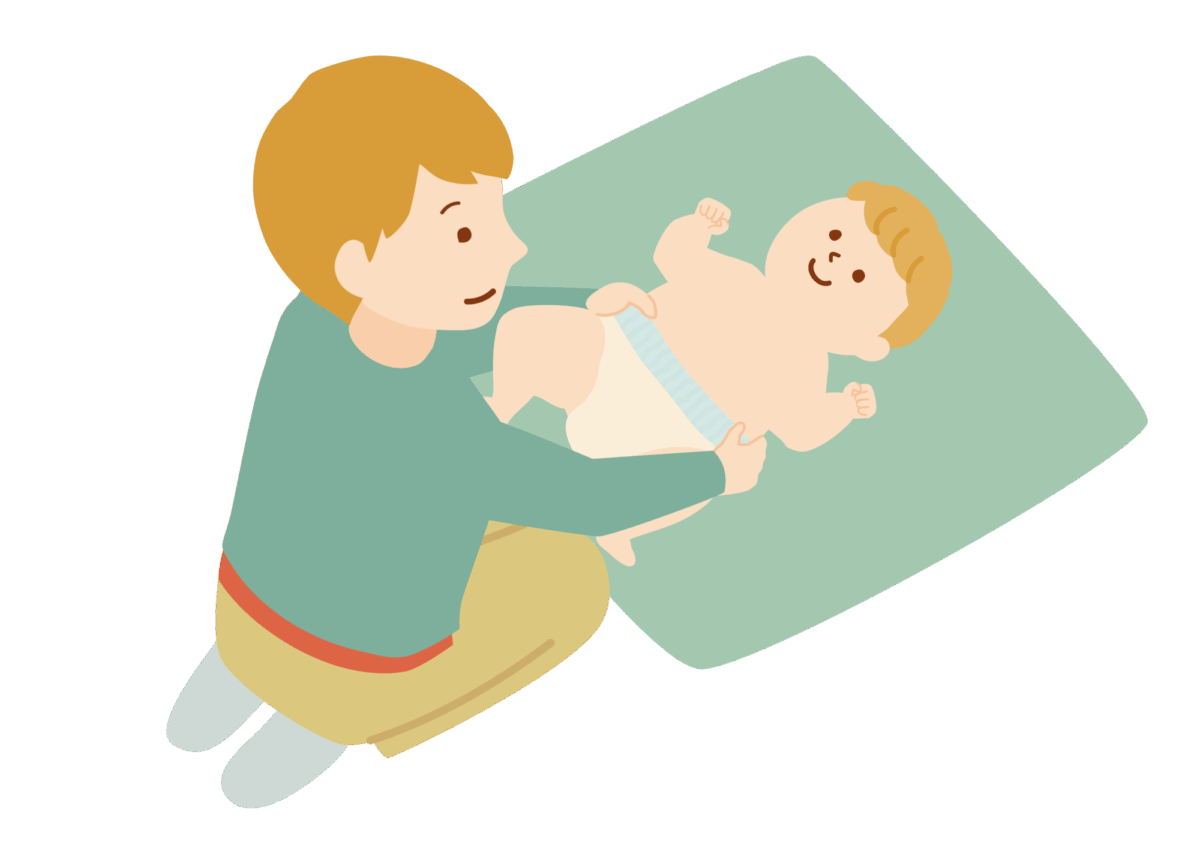 こまめにおむつ交換や洗浄などで皮膚を清潔に保ち、膿を排出する処置を行います。乳幼児の肛門周囲膿瘍は早期発見・早期治療が重要です。2歳頃までに多くの赤ちゃんは免疫機能を獲得して軽快していきますので、治療期間は数か月を要することが多いですが、根気強く治療を継続していきましょう。
こまめにおむつ交換や洗浄などで皮膚を清潔に保ち、膿を排出する処置を行います。乳幼児の肛門周囲膿瘍は早期発見・早期治療が重要です。2歳頃までに多くの赤ちゃんは免疫機能を獲得して軽快していきますので、治療期間は数か月を要することが多いですが、根気強く治療を継続していきましょう。
清潔を保つ
お尻の周りが不衛生だと、症状の悪化や再発を招く恐れがあります。そのため、こまめにおむつ替えたり、特にお通じの後は、温めのお湯で洗浄したりなど清潔な状態を保つようにしましょう。治療の中では最も重要です。
膿を出しきる
病状の悪化や再発を防ぐには、膿を完全に出しきる必要があります。まずは化膿を起こしている部分を針で切開して膿を排出させ周囲を圧迫し膿を出します。一度では膿を出しきれない場合は、排膿処置を繰り返し行います。
薬物療法
赤ちゃんの病状によっては、抗生物質の塗り薬や漢方薬の内服薬を使用することもあります。こどもの肛門周囲膿瘍は、抗生物質の塗り薬や内服薬は一般的ではありません。漢方薬は苦くて飲みにくいイメージがありますが、小さいお子様の場合は薬用のシロップと一緒に飲むなど工夫をするとほとんどのお子様は問題なく飲むことが可能です。漢方薬は飲ませることもありますが、必ずしも重要ではありません。一般的に下記の2剤が用いられています。
排膿散及湯
(はいのうさんきゅうとう)
鎮痛作用や排膿作用がある漢方薬です。患部が赤く腫れて強い痛みを伴っている場合に効果的です。
十全大補湯
(じゅうぜんたいほとう)
腸の免疫強化作用がある漢方薬です。排膿して皮膚表面の腫れが改善してきたころに使用することで、病状の再発を抑える効果が期待できます。