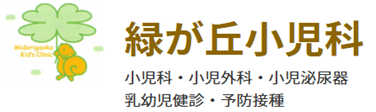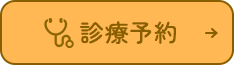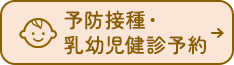「発熱・咳・嘔吐・下痢があるお子様」および「ご家族など周りに感染症(新型コロナ・インフルエンザ・RS ウイルス感染・ノロウイルスなど)の方がいる場合」は、必ず予約時に問診票へ記載をお願いします。
こどもの便秘について
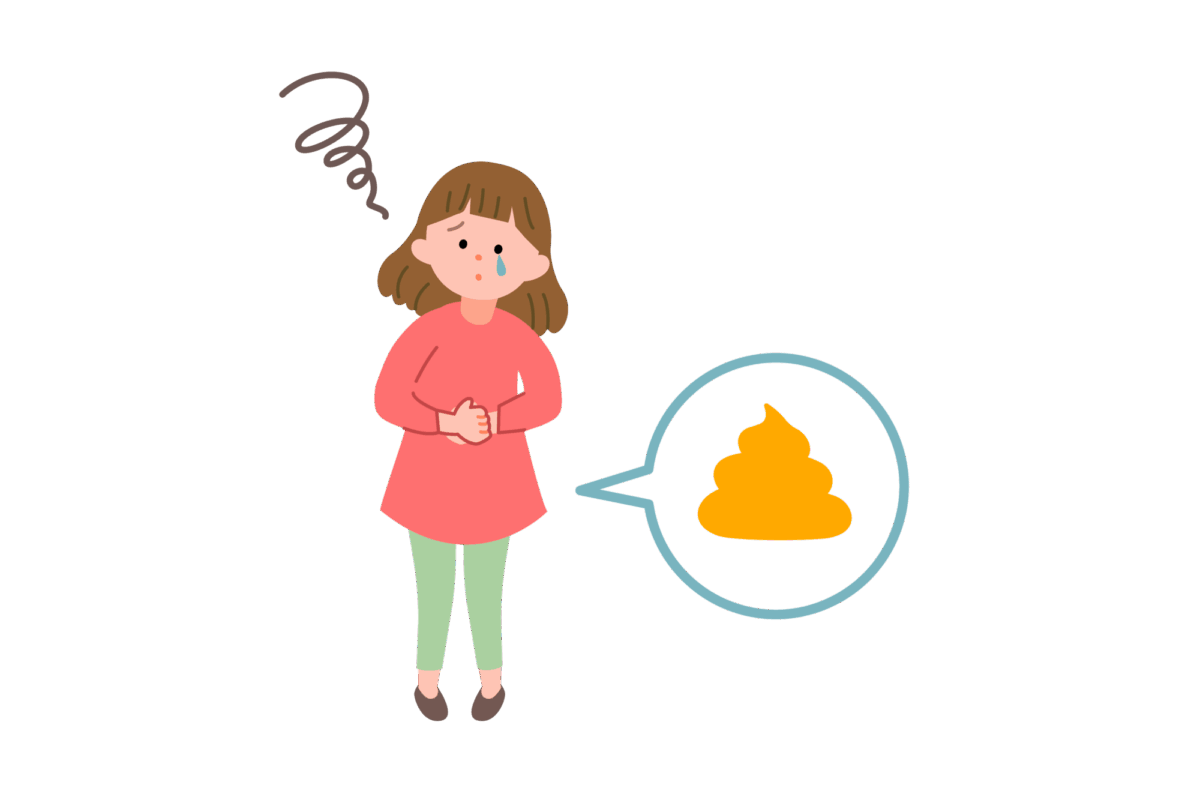 お子様の便秘は、様々な原因があり、治療方法やお薬の使い方も、年齢(月齢)や便秘の程度、原因によって異なります。便秘をそのままにしておくと、腸内に便が溜まり硬くなっていき、排便時に痛みを感じるようになります。この痛みがあることで排便を嫌がり、我慢するようになると、さらに腸に便が溜まり、腸管が広がることで便秘が悪化してしまいます。このような悪循環を繰り返すと、内服のみで排便を促すことが困難になり便秘が改善するまでに長い時間がかかることもあります。当院では、排便をスムーズにするための生活指導やトイレトレーニングのサポート、必要に応じてお子様の年齢や状態に合わせた便秘薬の処方を行っています。便秘の飲み薬や浣腸(坐薬)を使用するとくせになると考えている保護者の方もいますが、現在は、生理的に排便を促すお薬があります。学童以降まで、便秘が続くと腸管が弛緩し対応が難しくなります。また、年齢が上がるとトイレでの排便が上手くできるようなるお子さんがほとんどです。早期からの適切な治療が重要ですので、単なる便秘と軽く考えずに、気になる症状があればお気軽にご相談ください。まれに、お薬での対応が困難な排便障害もございますので、その場合は、専門の医療機関に紹介させていただきます。
お子様の便秘は、様々な原因があり、治療方法やお薬の使い方も、年齢(月齢)や便秘の程度、原因によって異なります。便秘をそのままにしておくと、腸内に便が溜まり硬くなっていき、排便時に痛みを感じるようになります。この痛みがあることで排便を嫌がり、我慢するようになると、さらに腸に便が溜まり、腸管が広がることで便秘が悪化してしまいます。このような悪循環を繰り返すと、内服のみで排便を促すことが困難になり便秘が改善するまでに長い時間がかかることもあります。当院では、排便をスムーズにするための生活指導やトイレトレーニングのサポート、必要に応じてお子様の年齢や状態に合わせた便秘薬の処方を行っています。便秘の飲み薬や浣腸(坐薬)を使用するとくせになると考えている保護者の方もいますが、現在は、生理的に排便を促すお薬があります。学童以降まで、便秘が続くと腸管が弛緩し対応が難しくなります。また、年齢が上がるとトイレでの排便が上手くできるようなるお子さんがほとんどです。早期からの適切な治療が重要ですので、単なる便秘と軽く考えずに、気になる症状があればお気軽にご相談ください。まれに、お薬での対応が困難な排便障害もございますので、その場合は、専門の医療機関に紹介させていただきます。
こどもの便秘の受診の目安
- 元気がなく、なんとなくぐったりしている
- 食欲がない、食べたがらない(便が数日出てないまたは少量しか出ないで食べる量が減っている)
- 排便の際に痛がったり出血したりして、排便を嫌がる
- トイレに行くのを避けようとする
- お腹がいつも張っている感じがする
- 排便の回数が1週間に3回未満
- 便は出ているが硬くてコロコロしている
など
便秘症とは?
便秘とは、長期間便が出なかったり、便が硬いために排便の際に痛みや出血を伴ったりする状態です。1日の排便の頻度やの食事の摂取量は人によって様々ですので具体的な期間は明確には定められていませんが、一般的に1週間の排便回数が3回未満の場合は便秘と言えます。また、毎日排便ができていても1回の排便量が少ない場合や兎糞便(コロコロ便)は便秘と診断されるケースもあります。
慢性便秘症とは?
上記のような便秘の状態が1か月以上継続していると慢性便秘症と診断されます。慢性便秘症かどうかは腹部の触診や超音波検査によって比較的簡単に診断できますので、お子様の便秘でお悩みの場合はお気軽に当院までご相談ください。
こどもの下痢について
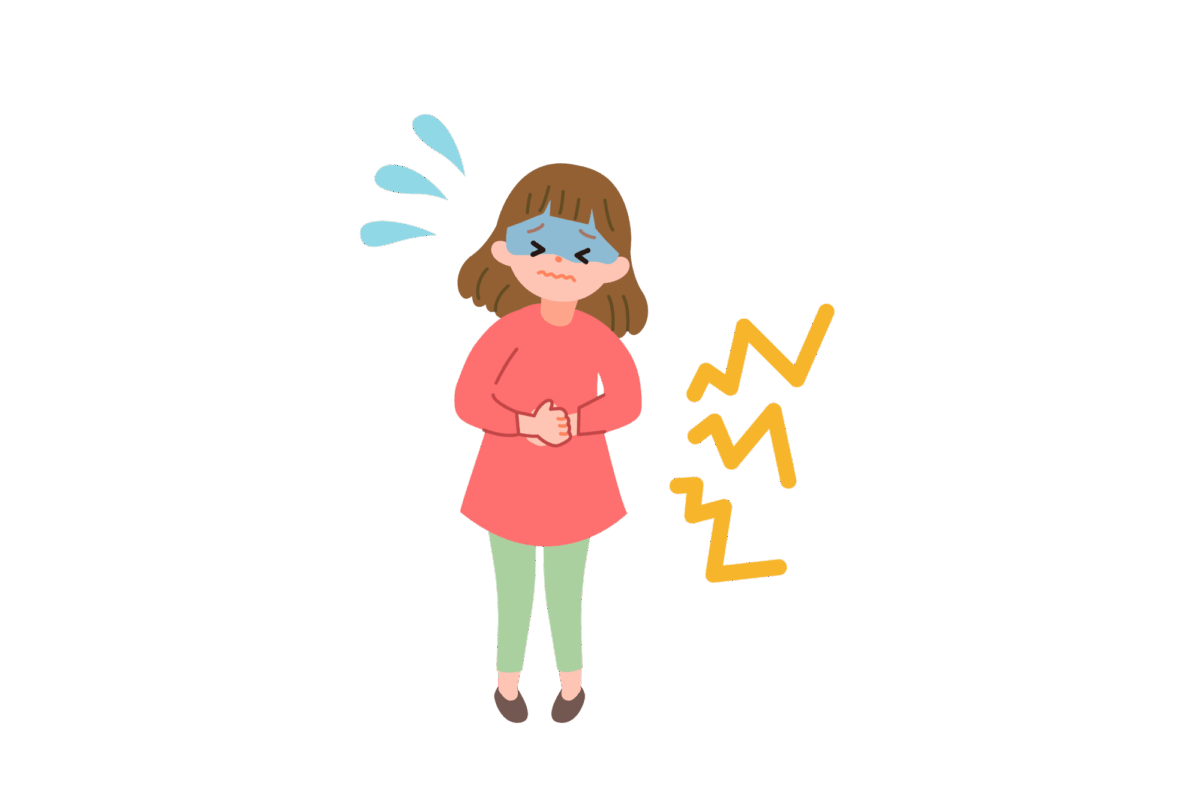 乳児期のお子様は消化機能が未発達なため、下痢することはよくありますが、必ずしもすぐに治療が必要になるわけではありません。排便の後も普段通りに母乳やミルクをしっかり飲み、機嫌よく過ごしているようであれば、過度な心配はいりません。ただし、翌日以降も下痢が続いたり、水分が十分に摂れずぐったりしている様子が見られる場合には、脱水や他の疾患の可能性もあるため、医療機関での診察が必要です。気になる症状があるときは、お早めにご相談ください。
乳児期のお子様は消化機能が未発達なため、下痢することはよくありますが、必ずしもすぐに治療が必要になるわけではありません。排便の後も普段通りに母乳やミルクをしっかり飲み、機嫌よく過ごしているようであれば、過度な心配はいりません。ただし、翌日以降も下痢が続いたり、水分が十分に摂れずぐったりしている様子が見られる場合には、脱水や他の疾患の可能性もあるため、医療機関での診察が必要です。気になる症状があるときは、お早めにご相談ください。
こどもの下痢の受診の目安
- ぐったりして元気がない
- 水分がうまくとれない、口の中が乾いている
- 下痢がなかなか治らない
- 嘔吐もしている
- 発熱がある
- 尿の回数が少なく、色が濃い
- 目がくぼんでいる
- 便に血が混じっている(血便)
- 便の色が白っぽい
- 便の臭いが普段と違う
- 下痢が続いておしりが赤くなり痛がる
など
下痢止めの使用について
こどもが下痢を起こす原因には様々なケースがあり、中には細菌やウイルス感染が原因の場合もあります。細菌やウイルスが原因の場合に市販の下痢止め薬を使用してしまうと、体内に細菌やウイルスが留まり続けて症状が長引いたり悪化する恐れもあるため、注意が必要です。お子様の下痢でお悩みの場合には自己判断で下痢止め薬を使用するのではなく、一度当院までご相談ください。1か月以上下痢が持続したり、血液が混ざる場合は、治療が必要な腸疾患が隠れている場合があり、対応が可能な小児の専門の医療機関を紹介いたします。
当院での排便管理について
お子様の便秘や下痢の原因は、生活習慣の乱れやストレス、器質的異常など様々なケースが考えられ、原因に応じて効果的な治療法も異なります。また、一言でこどもと言っても乳幼児から小中学生まで年齢層によっても原因や治療法は異なります。当院ではこれまでに様々な原因や年齢のお子様に対して診療を行ってきました。お子様一人ひとりに寄り添って生活習慣の改善指導や、病状をこれ以上悪化させないために必要に応じたお薬を処方しています。お子様の便秘や下痢などでお悩みの場合は、自己判断せずに一度当院までご相談ください。
こどもの嘔吐について
お子様にみられる吐き気や嘔吐の原因には、ウイルス性胃腸炎や胃食道逆流症などが主に挙げられます。
赤ちゃんの場合
赤ちゃんが少量の嘔吐をした後、問題なくケロっとしている場合や嘔吐を繰り返していてもミルクが飲めていて体重が増えている場合には特に心配は要りません。赤ちゃんはもともと胃の入り口である噴門の筋肉が未発達のため、ミルクを飲んだ際やちょっとした刺激を受けた際に嘔吐してしまうことが良くあります。嘔吐しても順調に体重が増加している場合、問題はありませんのでご安心ください。日頃元気な赤ちゃんさんが、嘔吐を繰り返す場合は、次のような疾患が考えられます。ただし、緑色の嘔吐(胆汁が混ざっている嘔吐)は、緊急を要する外科的な処置が必要な疾患があります。この場合は、対応が可能な小児専門医療機関を紹介させていただきます。
-
①胃食道逆流症
生後まもない赤ちゃんによくみられる疾患です。胃と食道の間(噴門)の水や食べ物の逆流を防ぐ筋肉が未発達なために起こりやすくなります。大人でもある疾患ですが、原因がが異なっており成長とともに筋肉が発達し自然に改善するのが一般的です。しかし、症状が重い場合で体重が増えない場合や気管支炎や肺炎を繰り返す場合は治療が必要です。赤ちゃんの症状は、機嫌がよくお腹もってないのに、ミルクを飲むと吐いたり、哺乳中または哺乳直後からゼコゼコしたりするなどを繰り返す場合には疑われます。まずは哺乳の指導や内服薬で対応します。
➁胃軸捻転症
新生児や乳児期の早期に多い疾患で、胃の固定が不十分で胃が通常の位置より捻転し、げっぷが出しにくい状態になることがあります。げっぷを出せないことでお腹全体が膨らみ、ミルクを吐きやすくなり、程度がひどいと体重が増えなくなります。元気なお子さんで、お腹の張りとミルクの嘔吐が見られる場合に疑われます。特に有効な内服薬はなく、まずは哺乳とげっぷの出させ方の指導を行います。ほとんどの場合は、生後3か月までに自然に改善します。
➂肥厚性幽門狭窄症
生後2週から1か月前後で発症する疾患で胃から十二指腸への出口(幽門)の筋層が厚くなり、哺乳後に嘔吐が見られ、時に激しい嘔吐(噴水状嘔吐)がみられます。元々元気ですが、放置すると体重増加不良や脱水症状を引き起こします。内服薬の治療もありますが、効果が不十分なことが多く、十分な量のミルクが飲めるまでに時間がかかります。そのため、治療は外科的治療が一般的で、現在は、目立たない創で手術を行うことができます。肥厚性幽門狭窄が疑われたら、対応が可能な専門施設を紹介させていただきます。
幼児の嘔吐の場合
 幼児の場合は、風邪を引いたり、胃腸炎を起こしたりすることで嘔吐しやすくなります。1歳を超えると嘔吐の頻度は減少しますが、嘔吐とともに発熱や頭痛、血便など他の症状がないか注意してみることが大切です。
幼児の場合は、風邪を引いたり、胃腸炎を起こしたりすることで嘔吐しやすくなります。1歳を超えると嘔吐の頻度は減少しますが、嘔吐とともに発熱や頭痛、血便など他の症状がないか注意してみることが大切です。
こどもが嘔吐したときの受診の目安
-
嘔吐と下痢を繰り返している
-
嘔吐を繰り返して元気がない
- 嘔吐とともにけいれんを起こし、意識がはっきりしない
-
頭を打った後に嘔吐している、または頭痛を訴えている
-
嘔吐物の色が、黄色や濃い茶色~黒、緑色をしている
-
嘔吐物に血が混じっている
-
唇や舌が乾いている
-
半日以上排尿が見られない
など
嘔吐したときの対応
嘔吐直後
縦抱きをして背中を優しくさすってあげましょう。ただし、揺らしすぎると吐き気を誘発しますので注意しましょう。眠りはじめたら、もう一度吐いてしまったとき嘔吐物が肺に入り込まないようにするため、顔や身体を横に向けてあげましょう。顔の近くにタオルなど窒息の原因になりえるものは置かないように注意してください。
吐き気があるときや、嘔吐した直後は口をゆすぐ程度にして、しばらくの間は腸を休ませてあげましょう。水分を無理に飲ませる必要はありません。吐き気が落ち着いてから水分は与えますが、最初は、室温以上の水・お茶・経口補水液などを少量で時間を空けながらゆっくり与えてください小さいお子さんは与えた分だけ飲んでしまい、嘔吐を繰り返すことがあります。この場合は、飲んだ以上に水分やミネラル(電解質)が失われますので、なるべく吐かせないように対応することが重要です。ほとんどが、時間がたつと少しずつ水分や食事が摂取できるようになりますが、与えるものを選ぶ必要があります。
臭いによって、再度吐き気を誘発することがあります。吐き気が落ち着いてきたら、嘔吐によって汚れた衣服は交換しましょう。
水分
嘔吐を繰り返すと、脱水症状になりやすいため、少しずつ水分を摂取することが大切です。最初は嘔吐の1~2時間後を目安に、スプーン1杯(約5ml)程度の水分摂取から始めましょう。その後、お子様の様子を見ながら5〜15分おきに飲ませていき、特に問題がなければ少しずつ量を増やしていきましょう。飲ませるものは、経口補水液や味噌汁の上澄みなどが良いですが、難しい場合には水やお茶でも構いません。また、母乳を直接飲ませると飲み過ぎてしまう恐れがあるため、飲ませる際には搾乳してからごく少量ずつ与えるようにしましょう。その他、ミルクや果汁入りの柑橘類、炭酸飲料、固形物などは胃腸の負担が増して症状を悪化させる恐れがあるため、体調が回復するまで控えるようにしましょう。
食事
水分摂取がしっかりできるようになったら、消化に良いおかゆやうどんなどで少しずつ食事を再開しましょう。
家庭内感染の予防
ノロウイルスやロタウイルスなど感染による嘔吐の場合は、どちらのウイルスも感染力が非常に強く、症状が治まっても感染者の糞便や嘔吐物に大量のウイルスが残っているため、適切に処理することが重要です。ウイルスはアルコールに強いため、「次亜塩素酸ナトリウム」と表記してある家庭用の塩素系漂白剤や哺乳瓶用の消毒液などを使用します。嘔吐物が酸性のため、次亜塩素酸ナトリウムを原液のまま使用すると有毒なガスが発生する可能性がありますので、必ず薄めて使用してください。
嘔吐物が直接ついてしまった場所の消毒液の作り方
家庭用の塩素漂白剤:10ml
(ペットボトルのキャップ2杯分)
+水:500ml
(500mlのペットボトル1本分)
ウイルスは乾燥すると空気中に漂い、吸い込むことで感染する可能性があるため、窓を開けて換気し、可能であればマスクと使い捨ての手袋を着用します。準備が整ったら、汚染範囲を広げないように内側に寄せてペーパータオルで拭き取ります。嘔吐物が付着した床などに消毒液をかけて拭き取ります。
その他、ご家族が嘔吐した際に塩素系漂白剤が手元にない場合には、できるだけ早く嘔吐物を処理し、石鹸で十分に手洗いをしてください。衣服に嘔吐物が付着した場合には、入念に水で洗い流してから洗濯するようにしましょう。